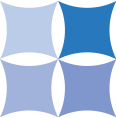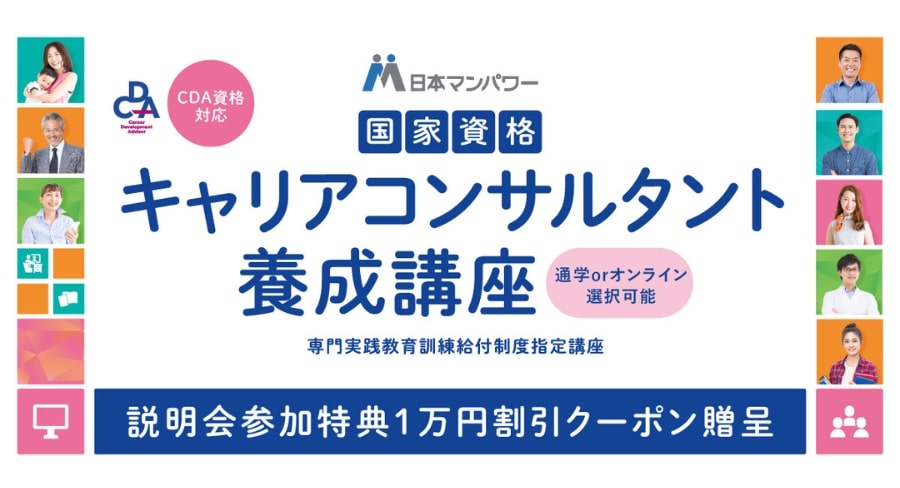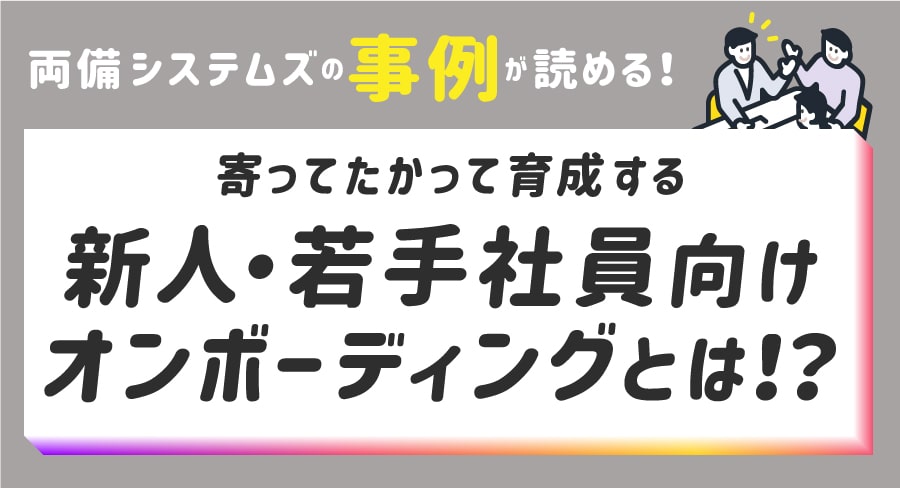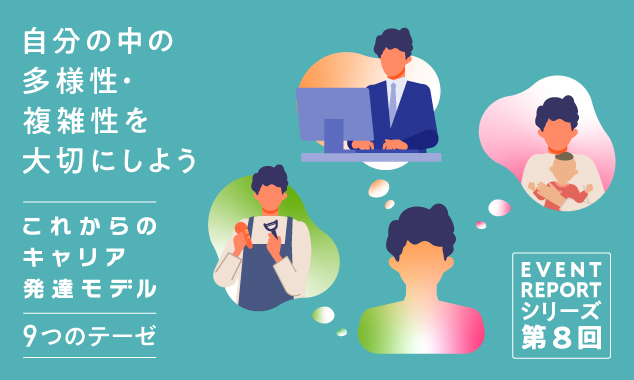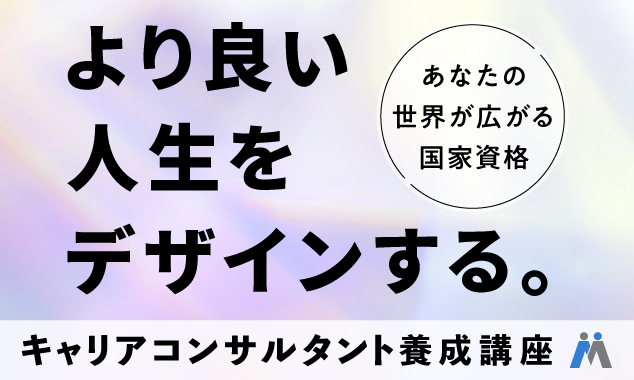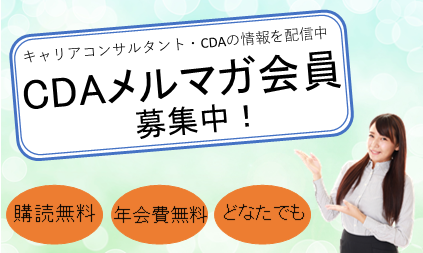「これからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~」の内容をご紹介するイベント。今回は、9つのテーゼの中の『多様性と複雑性を大切にしよう』を取り挙げます。
イベントでは、最初に、MBTIを日本に広めた第一人者である園田由紀先生からお話を伺いました。その後「キャリアのこれから研究所」のプロデューサー酒井章氏、研究所所長の水野みちも交えてパネルディスカッションを実施。その後、参加者の皆さまと共に豊かな対話の時間を持ちました。
●イベント実施日 2024年11月27日
●「これからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~」詳細ページは、こちら
●執筆:原博子 キャリアカウンセラー
主催者からの挨拶
2日本MBTI協会代表理事 園田由紀先生登場
3園田先生のお話
(1)ペルソナという役割性格について
(2)キャラクターと役割性格
(3)自分のキャラクターを知ることが大切
(4)ギフト~自分という素晴らしい命をもらって、この世にあなたしかいないような個性を刻み込まれてこの世に誕生している~
自己の声を聴くことができるように人間の心の構造は出来上がっている
(6)自分の人生を生きるために、他者と比べるのをやめる
(7)「自分らしさ」でなく「自分」を生きよう
(8)気づきの語源は「傷つき」。傷ついた分、成熟している
(9)自分自身を知るということは、自分が自由になるということ
4酒井氏から園田先生への問いかけ
5水野から~すでにある自分の中の多様な自分を活かせるようになる~
6参加者の皆さんとの対話
7園田先生から最後のひとこと
1主催者からの挨拶

キャリアのこれから研究所
所長 水野みち
水野:いま私たちが生きている時代は、変化が激しく、将来の見通しも立てにくく、あいまいなことが増えています。
こうした時代の中で、「キャリア」の考え方も変わってきました。
今の私たちに求められているのは、ただ変化に対応するだけでなく、自ら変化していく力、そして柔軟に形を変えられる力(変幻自在さ)です。
私たち一人ひとりが、本来持っている多様性や複雑さ、そして「人は変化し、成長できる存在である」ということを、あらためて思い出して、その力を発揮していこう。――今回のイベントは、そんな想いから企画されました。
一方で、こんな疑問も湧いてきたりもします。
「変幻自在」であることは大切ですが、そればかりを追い求めすぎると、苦しくなってしまうこともあります。
まわりに合わせてばかりで、自分の気持ちや考えを見失ってしまうと、まるで糸の切れた凧のように、どこに向かっているのか分からなくなってしまいます。
キャリアの研究者であるダグラス・ホール博士も、「キャリアには、適応力だけでなく、アイデンティティ(自分らしさ)も同じくらい大切だ」と言っています。
――自分は本当はどうしたいのか? どんな人間なのか? 何を大切にしているのか?
こうした問いに向き合うことが、今あらためて求められているのではないでしょうか。
変わっていく自分、そして自分の中にある多様性や複雑さ。
一方で、変わらない「自分」とは?
私たちは、これらをどう捉え、どう育てていけばいいのでしょうか?
こうしたテーマを深く掘り下げるために、今回のイベントでは、この分野に精通されている園田由紀先生をお招きしました。
園田先生は、MBTIを日本に広めた第一人者でもあります。
それではここから、園田由紀先生にご登壇いただき、「一人ひとりが持つ力」や「多様で複雑な自分に目を向けることの意味」について、くわしくお話を伺っていきたいと思います。
2日本MBTI協会代表理事 園田由紀先生登場

園田由紀氏
一般財団法人日本MBTI協会代表理事/東京大学大学院医学研究所非常勤講師
京都大学大学院医学研究所非常勤講師/ユング派臨床心理士
園田:今日は「自分の多様性と複雑性」というテーマをふまえ、最初の投影資料の背景に荒波を選びました。まずはその理由からお話をさせていただきたいと思っています・・・。
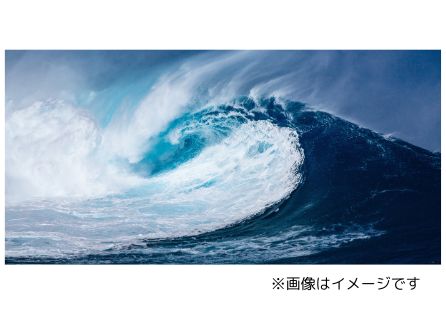
~このようにお話をはじめた園田先生。平常心を保ちながら、今、ご自身の心の中には荒波が起きている、という自己開示をしてくださいました。その冒頭の言葉から、心というものの奥深さをあらためて感じる時間でした。~
3園田先生のお話
(1) ペルソナという役割性格について
園田:私たちは「ペルソナ(役割としての性格)」を、たくさん持っています。
特に日本人は「ペルソナ文化」とも言われるほど、さまざまなペルソナを上手に使い分けていると感じます。
私自身、長くアメリカで教育を受けていたのですが、日本に帰ってきたときに、人々がその場その場で驚くほど自然にペルソナを“脱ぎ着”して適応している姿に、感動すら覚えたのを今でもよく覚えています。
この「ペルソナ」は、社会の中でうまく生きていくために、年齢を重ねるごとに増えていくものです。そしてそれは決して悪いことではなく、むしろ生きる上で必要なものでもあります。
ただ、気をつけたいのは、ペルソナが心地よくなりすぎることです。
たとえば、管理職になったばかりの方々に向けた研修の中でよくお話しするのですが、「管理職」というペルソナを身につけると、その役割にぴったりとフィットして、つい脱ぐのが嫌になってしまうことがあります。
そのままの“管理職モード”で自宅に帰ると、家族に「私はあなたの部下じゃない!」と怒られてしまう、という事例もたくさんあるんです。
これはまさに「過剰適応」の状態です。
本来、ペルソナは自分で自由に脱ぎ着できるもの。
けれど、ひとつのペルソナに安住しすぎると、それが自分の“顔”にぴたっと貼りついて、簡単には脱げなくなってしまう。
それは、自分自身も息苦しくなるし、まわりの人も苦しくさせてしまいます。
園田:人間には、「ペルソナ(仮面)」がある一方で、その奥には必ず「素顔」があります。
この素顔=本来の自分にあまり目を向けずにいると、「ペルソナの闇」が強くなってしまうことがあります。
つまり、自分の中にある「嫌な部分」や「目をそらしたくなる部分」と向き合わずにいると、知らないうちに、それらを避けるクセがついてしまうのです。
でも実は、その「嫌な部分」こそが、自分を成長させるための大事な“種”なんです。
きちんと向き合って、乗り越えることができれば、心の成熟につながります。
しかし、それを避け続けていると、その部分だけがひとり歩きして肥大化していくこともあります。
そうしたときに起こるのが「投影」という心の働きです。
投影とは
・自分の心の中にある感情や資質や欲望を他者がもっているものと認知する現象
・特に自分のなかにある受け入れがたい自分を排除しようとして、無意識に抑圧している「見たくない」自分を他者に見る現象。
(2) キャラクターと役割性格
園田:そもそも、「性格」や「パーソナリティ」とは何でしょうか?
先ほどお話ししたように、人には「役割としての性格(ペルソナ)」がある一方で、「素顔」ともいえる本来の自分も存在します。
心理学では、この、「人の性質」を大きく「性格」と「人格」の2つに分けて考えることができます。
まず、「性格」というのは、英語でいうと「キャラクター(character)」のことです。
この言葉はラテン語で「生まれつき刻み込まれたもの」という意味を持っていて、生まれながらに持っている気質や傾向を指します。
一方、「人格」や「パーソナリティ(personality)」という言葉の語源は「ペルソナ」、つまり仮面や役割にあります。
これは、生まれた後に身につけていくもので、社会の中で生きていくうえで必要な行動の特徴や言動のパターンを指します。
性格って?Personalityって?
- 性格(キャラクター)=生まれ持った気質や傾向
- 人格(パーソナリティ)=社会に適応する中で後天的に身につけた振る舞い方や役割的な性質
(3) 自分のキャラクターを知ることが大切
園田:私たちは、「キャラクター(生まれ持った性格)」と「パーソナリティ(後から身につけた性格)」の両方をあわせ持っています。
この2つが相互に作用し合いながら、今の“自分”というものが出来上がっています。
そして、何より大切なのは「自分のキャラクター=生まれ持った性質」を知ることだと言われています。
なぜなら、そこに「自分らしさの源=自分たる所以(ゆえん)」があるからです。
心理学者のユングも、次のように語っています。「赤ちゃんは白紙の状態で生まれてくるわけではない」と。
もし本当に白紙の状態で生まれてくるのであれば、同じように育てれば、誰でも同じように育つはずです。でも現実には、同じ親に育てられた兄弟姉妹でも、まったく違う性格に育つことはよくありますよね。同じような道を進まなかったり、同じ親から生まれたとは思えないぐらい全然違う印象だったりします。
これはつまり、人は白紙ではなく、“その人らしさ”が最初から刻まれて生まれてくるということなのです。
ユングのこの考え方は、よく花の“種”に例えられます。どんな花が咲くか、という要素は全部種の中にある。ただし、どんな土に植えられ、どんな光や水を受けるか――つまり、外からの影響(環境)によって花の咲き方は大きく変わるのです。

(4)
ギフト~自分という素晴らしい命をもらって、この世にあなたしかいないような個性を刻み込まれてこの世に誕生している~
園田:その人がその人であるいう所以、それを「ギフト」という言葉によく言い換えます。最近日本では、障害を持たれている方は「Gifted people」と言うそうですが、本当は我々みんながギフテッドなんです。1人ひとりが素晴らしい命をもらって、この世にあなたしかいないという個性をちゃんと刻み込まれて、この世に誕生しているんだということです。
ユングはそれをどう考えたかというと、意識の真ん中に「自我」という自分自身のコアな部分があるのならば、無意識の真ん中にも何かがあるはずだと。それをユングは「自己(Self)」と名付けたんですね。
つまり「セルフリアライゼーション(self realization)が人生のプロセスそのものだ」とユングは言いました。
日本語に訳すと「自己実現」になります。それは、マズローが言う自己実現よりも、もう少し深い意味合いがあります。
(5) 自己の声を聴くことができるように人間の心の構造は出来上がっている
園田:人間は、心の奥深いところに「自分であり続けるための衝動」をしっかりと持っている、とユングは言っています。例えば誰かと会おうと思って約束をしたものの、どうしても会えないとか、会社と面談があったのに何かの都合で遅れて面談に行けなかったとか。これらも実は自己の声だ、という風に解釈すると、実はそこは行ってはいけない場所だったんだ、とも考えられる。
つまり、自分に起きたことで無意味なことはない、ということです。意味をもたらす力は誰にでもある。ユングは「偶然というのは、起こるべくして必ず起きる、起きていることをあえて考えてみることで、自己の声を聞けるように人間の心の構造は出来上がっている」と言っています。
(6) 自分の人生を生きるために、他者と比べるのをやめる
園田:ですので、自分の人生を本当の意味で生きていくためには、まずは他者と比べるのをやめることが大切です。
その上で、「ペルソナ(役割としての自分)」と「キャラクター(本来の自分)」を切り分けて捉えること。そして自分の思い込みとも距離を取ってみることが必要になってきます。
たとえば、「自分ってこういう人間だ」と思っていることも、よくよく見つめ直すと、
それは単なる思い込みだったり、昔誰かに言われた一言を鵜呑みにして、自分だと信じてしまっている可能性もあります。
もしかしたら、それは自分の“認知の偏り”かもしれないのです。
また、自分と他者をきちんと分けて考えること(自他の分離)もとても大切です。
「自分」と「他者」は違う存在であるということを、明確に理解しておくことは、精神的な成長の上でも欠かせないポイントです
このように、自分という存在が他と混ざらずにしっかりと立つことで、「自我の確立」が生まれていきます。
そして、人と比べず、「この世に1人しかいない自分自身」に意識を向けることで、
ようやく、“自分の人生”を自分の足で歩いていくことができるようになるのです。
(7) 「自分らしさ」でなく「自分」を生きよう
園田:最近よく「自分らしく」とか「自分らしさ」という言葉を聞きます。しかし自分らしさにこだわりすぎると、今度は自分らしくあろうということにがんじがらめになってしまいます。
自分らしさの「らしさ」を取って「自分を生きる」というふうに、見方を変えてみることを私は大切にしています。
「らしさ」がなくなると、性別も年齢も関係なくなって、「自分という大事業を生きる」ようになっていきます。
(8) 気づきの語源は「傷つき」。傷ついた分、成熟している
園田:「自分の人生の経営者は、自分自身である」そう認識できるようになると、自分が持っているリソース(時間・能力・体力・感情など)を正しく理解し、最大限に活かしてアウトプットできるようになります。
つまり、自分自身としっかり向き合う力が養われてくるのです。他人と比較するのではなく、「個」としての自分自身に向き合い、自分が見ている世界と、他者が見ている世界とではどれだけ違うのかを、冷静に理解する機会も得られるようになります。
また、自分の「認知スタイル(ものの見方・考え方の傾向)」を超えて、普段使っていない第三機能や劣等機能と向き合い、それらを開発していくことで、認知の幅がどんどん広がっていきます。そのプロセスに向き合う“覚悟”を持つことで、これまで無意識にあった自分の側面にも、少しずつ気づけるようになってくるのです。
ちなみに、「気づき」という言葉の語源は、「傷つき」と言われています。
無意識にあるものは、私たちが「傷つきたくない」と思って避けている部分でもあります。
だからこそ、何かに気づくということは、時に少し痛みを伴うものなのです。しかし、それは「成長痛」とも言われるように、その痛みの分だけ、私たちは成熟している・成長しているとも言えます。
「傷つくこと=悪いこと」と捉えるのではなく、「その経験が自分を育ててくれているんだ」と捉え直すだけで、傷ついた出来事も、忌み嫌うことなく、自分の成長と結びつけて前に進めるようになっていくのではないでしょうか。
●主機能
個人が最も信頼している心で、使う事で動機付けられる。その意図の得意な世界で用いられる
●補助機能
主機能を補佐し、心のバランスをとる機能。そのため主機能が知覚機能(感覚か直観)なら補助機能は判断機能(思考か感情)、主機能が判断機能なら補助機能は知覚機能となる
●第三機能
主機能と補助機能を補佐する心
●劣等機能
個人が最も信頼していない心で、最も注意が向けられない心。そのため個人の中で最も発達していない心。主機能の対極の機能である、かつ主機能の対極の世界で働く。
(9) 自分自身を知るということは、自分が自由になるということ
園田:意識の領域を広げると、自分で自分の視点をコントロールできる領域が増えるので、自分の認知に偏りがあるなと思うと反対の機能をあえて使うことで、現実をちゃんと見ようとすることもできます。人はペルソナをたくさん持っていますが、ペルソナ優位でやっていくと、自分が糸の切れた凧のようにどこに行ってしまうか分からない、ということが起きるかもしれません。しかし、自我を持ち、この場ではこのペルソナを使おう、この場ではこのペルソナを脱ごう、というようにできるようになると、自分のコントロール下で使う表現の仕方がたくさん生まれます。
たくさん選択肢があるということは、より自分が自由になるということです。そういう意味でも自分自身を知るということはとても重要になってきます。
4酒井氏から園田先生への問いかけ

酒井です。キャリアこれから研究所の設立に関わり、現在プロデューサーという形で関わらせていただいています。
まず、MBTIを日本に導入された園田先生の「想い」のようなものをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか?

私自身がアメリカでずっと過ごして日本に戻ってきたときに、日本人の自己肯定感がとても低いことに気付いたのですが、その理由がよくわからなかったんですね。
話を聞いていくと、どうしても人と比べるという癖がある。特に偏差値という文化の影響があるのか、自分に焦点を当てるよりは他者に焦点が当たって自分を見ている、ということがわかってきました。そのため他者焦点ではなく、自分だけに焦点を当てたMBTIというものを日本人に伝えることの必要性を感じました。
元々自分の中にある心のパターンを意識してもらうことで、自分にしかない魅力や、自分にしかない課題に気付いてもらえるようなきっかけになると良いと思ったからです。日本人は、もともと集団になったときの強さは秀でているので、それに個の力が加わったら、最強になるとも感じました。
日本人1人ひとりが持つ力に気づいていただけるきっかけになれば、導入した甲斐もあるな、というのが私の想いになります。

「日本人はペルソナを使いこなせることが強み」だとお話になりましたが、少し詳しくお聞かせいただけますか?

MBTIのフィードバックをドイツ人の会社で行ったことがありました。参加者にキャラクターとパーソナリティの話をした時のことです。皆さん「ペルソナって何だ?」という質問をするんです。「どういうことですか?」と聞いたら、「僕たちはキャラクター(本来の自分)で生きているから、ペルソナ(役割としての仮面)はよく理解できないよ」と仰って。文化の違いというのはこういうところにも出てくるのかなと思いました。
一方、日本では「ペルソナ(役割としての仮面)」はすごくわかるけれど「キャラクター」と言われるとアニメなどの「キャラクター」を連想します。つまり、自分のキャラクターなんて考えたことがない、というケースが多いです。
アメリカやヨーロッパと比較すると、日本人はペルソナとキャラクターを区別することに時間を費やしことが必要なことが多いです。そのためMBTIのベーシックなフィードバックでも最低でも4時間ほどかけて、ペルソナを自らはがしながら自分の素顔を体験的に見出していただいた後、2日間かけてダイナミクスの演習をして劣等機能の開発のところまでさせていただくと、ようやく自分の劣等機能が動いていないことを体感したり、「本当の多様性」というものに深く気づかれたりします。こうした経験を通じて、日本はペルソナがものすごく求められている文化であり、とても上手にペルソナを使い分けているのだと感じます。

世間にMBTIと似て非なるものが出回っていることに問題意識を感じていらっしゃるとお聞きしました

はい。最近では、インターネット上に無料で簡単に受けられるMBTIの“偽物”が多く出回っていることに心を痛めています。
実際に、そうした診断を提供しているソフト開発会社にも連絡を取ってみたのですが、信頼性(=一貫性があるかどうか)のデータはあっても、妥当性(=本当に測るべきものを測っているか)のデータは提供できないとのことでした。おそらく存在しないようです。
妥当性がないということは、何を測っているかがはっきりしていないということであり、それを根拠に「自分は◯◯タイプ」と信じ込んでしまうのは非常に危険です。

特に若い人ほど、自我がまだ確立していない傾向があるため、診断された「タイプ」に合わせた自分を演じるようになってしまい、結果的に本来の自分からどんどん遠ざかってしまうことになります。
つまり、誤った自己理解が、誤った自分を強化してしまうということです。そうなると、心のエネルギーは枯渇し、無意識のうちに疲弊してしまいます。そうすると、自己不一致がどこかの段階で起こってしまいます。そして、大きな危惧は、自分自身を受け入れることが難しくなり、同時に他者を受け入れることも難しくなっていきます。
ここでお伝えしたいのは、「無料で簡単に自分のことがわかるほど、人間は単純ではない」ということです。
こうした大切な考えを、今後も様々な場面で発信していかなければならないと感じています。
なぜなら、こうした安易な診断により、人間を“単純化”してラベルを貼ってしまう傾向が、これからの若い世代に広がっていくことに、強い危機感を抱いているからです。

かつて日本では、「A型だから几帳面」といったように、血液型で人をレッテル貼りする文化がありました。実際に、そうした決めつけによって傷ついた人も多かったはずですが、そういった事実はあまり公に語られていません。
だからこそ、過去の昭和的な“人間の単純化”という習慣に戻らないでほしいですし、現代社会はもっとグローバルの視点で自分を生きる必要性がある時代ということを念頭に、英語力云々の前に、客観的に自分自身をしっかりと分析して、自分を語る言葉を沢山持てるようになって、自分たるゆえんをもつ欧米諸国や他国の人々と平等に渡り合えるようになってほしいと心から願っています。
~「今日ご参加のキャリアコンサルタントの皆さんへのメッセージを」という酒井氏からの言葉を受けて、園田先生から以下のようなコメントがありました。~

「職業や仕事のマッチングといった、キャリアコンサルタントじゃなくてもできることではなく、キャリアコンサルタントだからこそできる、“その人の自己理解やアイデンティティの確立”の支援をぜひやってください」
5水野から~すでにある自分の中の多様な自分を活かせるようになる~

改めて園田先生のお話を聞くと、心のエネルギーが高まるのを感じます。自分自身がしっかりと「自我」を持ち、自己理解を深めることで、実はより「柔軟」になっていけるという点が、とても興味深かったです。
強く思い込みを抱え、無理に見ようとしない心の硬さが、「ほどけていく」ことで、もともと自分の中にある多様な自分自身を活かせるようになる。そうしたメカニズムの大切さを改めて実感しました。そして、キャリアコンサルタントの養成団体として、この考えを大切にプログラムを維持・構築していく使命をより一層強く感じています。
今回、園田先生から、大切な心の働きを教えていただきましたが、皆さんはどんな点が心に響きましたか?
また、もっと知りたいと思うことはありましたか?
6参加者の皆さんとの対話
~数名の参加者の方々がお声を聴かせてくださいました。
この日はたくさんの「MBTI認定ユーザー」の方が参加されていたのですが、その発表を受け、園田先生から、参加された「MBTI認定ユーザー」の方へエールのような言葉が届けられました。~

花束を渡すことができる存在になれるのがMBTI認定ユーザー
例えば、集団の中でマイノリティ(少数派)になった人っていうのは、その場に居辛らかったり、自分の存在や声を小さくしてしまうことがあります。しかし、マイノリティだからこそ見えているものがあるのです。そうした意見を吸い上げることができるのが、このタイプ論に成熟していった人なのです。
元々民主主義というのはマイノリティの声をちゃんと聴く、というところから来ているので、組織にタイプ論は貢献できると思います。チームの成熟への貢献など、いろんな方法を認定ユーザーは提案できます。
その場でマイノリティとなった人が発言したら「その視点は全く考えてなかった。ありがとうございます」と、その人のいることの価値を高める、言葉の花束を差し上げてほしいんです。そういう視点を持たない人の方が多いと思います。認定ユーザーは「そういう多様な視点も与えてくれてありがとう」と言ってくれる存在なのです。そういう場をぜひ作っていただきたいと思います。

改めて、キャリアコンサルタントも、社会や組織の中のマイノリティの声、声にならない声を吸い上げることができる大切な役割なのだと思いました。
7園田先生から最後のひとこと

自分が認識していなくても、心は成長したいと思っています。そこにまず目を向けていただきたいと願っています。先ほどお話ししました「自分らしく」ではなく「自分を生きる」というふうに考え直していただくと。世界や人間関係の見方が変わってくると思います。
「自分を生きる」というと何か覚悟が必要になってくるようなイメージが出てくると思います。でもそれは生きる覚悟とイコールだと私は思っていますので、多くの人がそういう覚悟を持って自分の人生を生きて、人間関係を作ってくださると、もう少し世の中にそれぞれの方の居場所ができてくると思っています。
今日はありがとうございました。

園田先生、深く、慈愛に満ちたお話をありがとうございました。皆さま、ありがとうございました。
[参考リンク]
今回のように、自分自身と向き合ってみたいと感じられる方には、
MBTI公開体験セッション ベーシック編が大変お勧めです。
また、誰かを支援することに興味がある方には、「キャリアコンサルタント養成講座」もお勧めです。第31回が開講間近です(7月開講)。まずは説明会にご参加ください。
キャリアカウンセラー&社労士。趣味は映画・ドラマ鑑賞、ヨガ。ヨガの得意技は頭のてっぺんで立つポーズ。
この記事はいかがでしたか?
ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!
RECOMMENDED関連おすすめ記事
人気記事
-
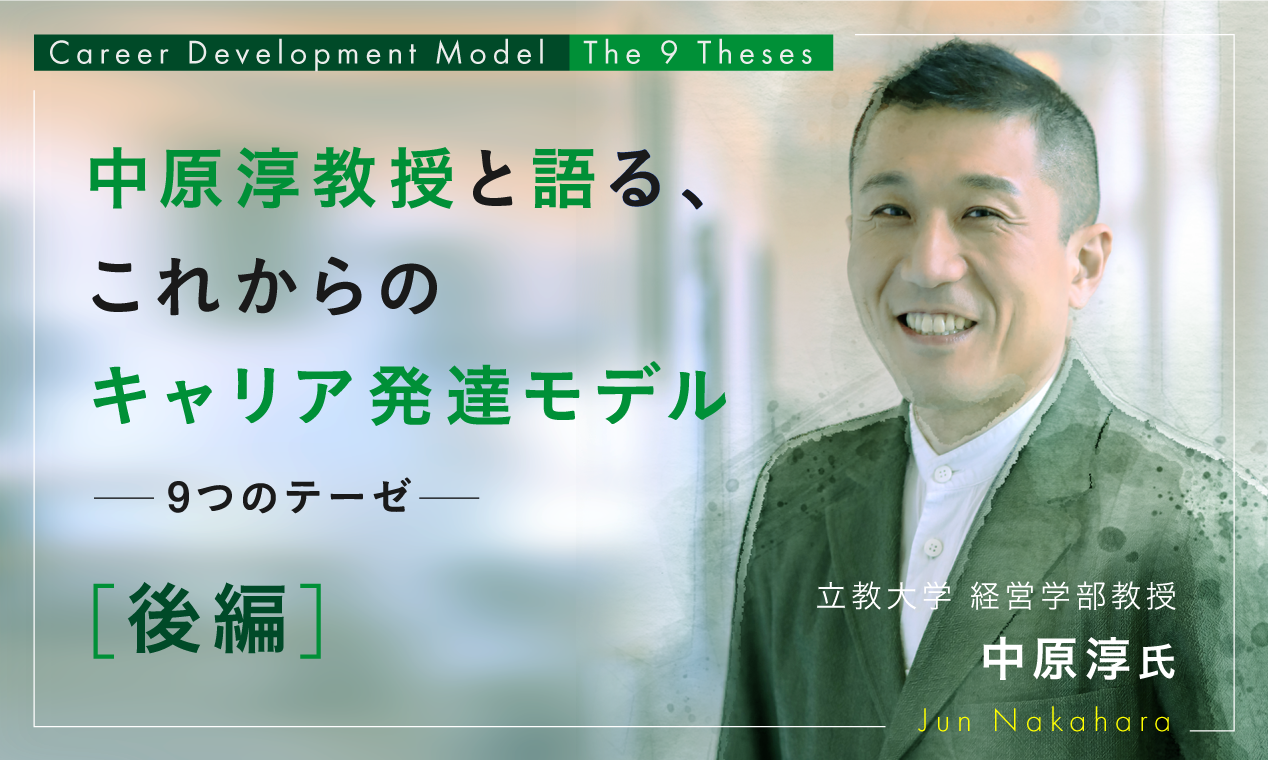
PICK UP
イベント
【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~
2022.8.29
-

PICK UP
イベント
【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~
2022.4.22
-
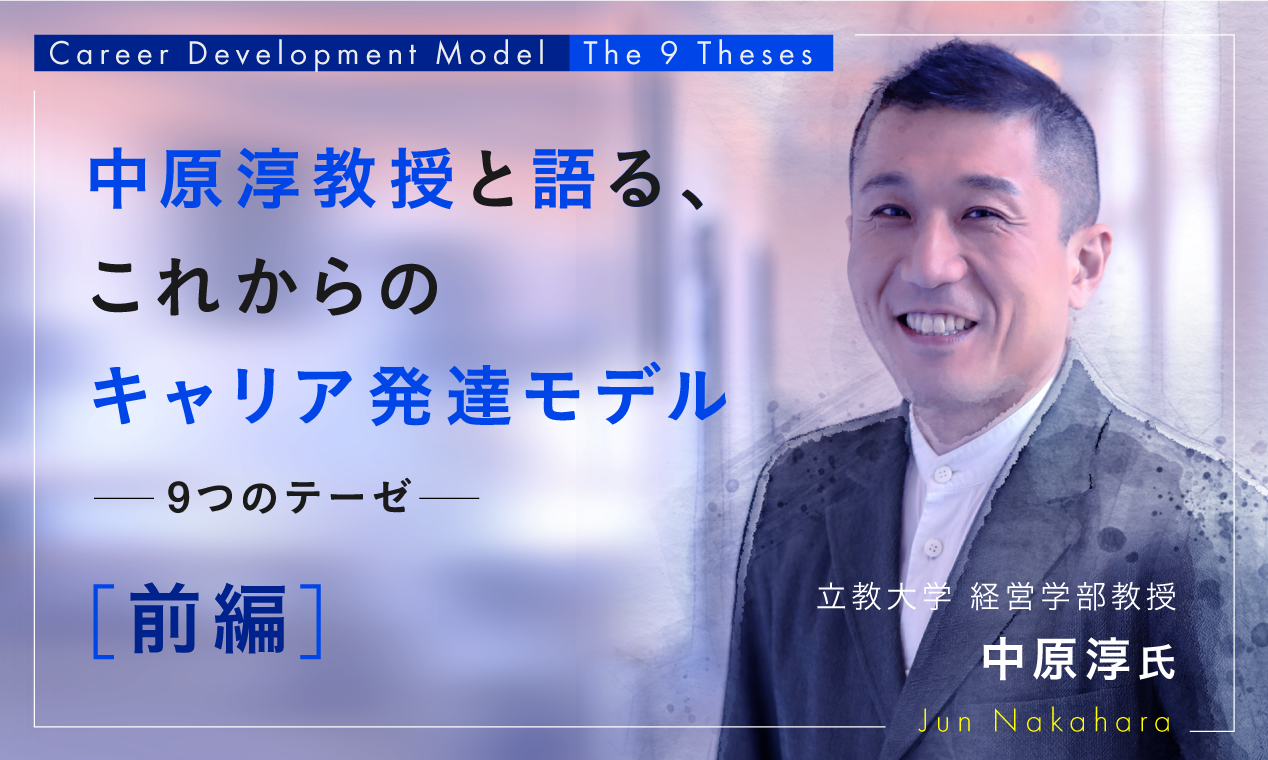
PICK UP
イベント
【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~
2022.4.19
-
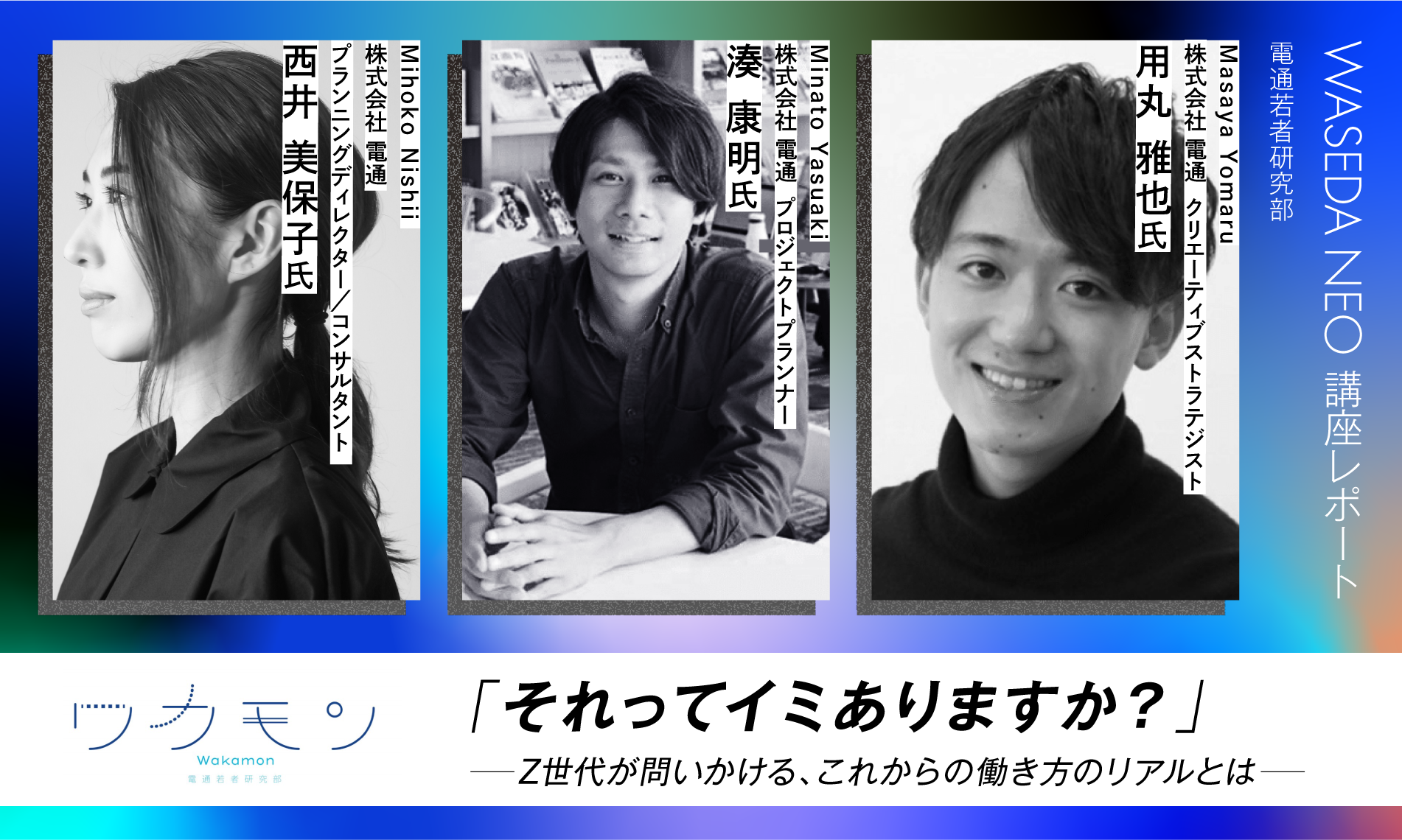
イベント
「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-
2022.2.8
-

PICK UP
特集記事
ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり
2020.12.28
-

インタビュー
個人
マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)
2020.12.4
-

インタビュー
個人
マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)
2020.10.30