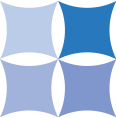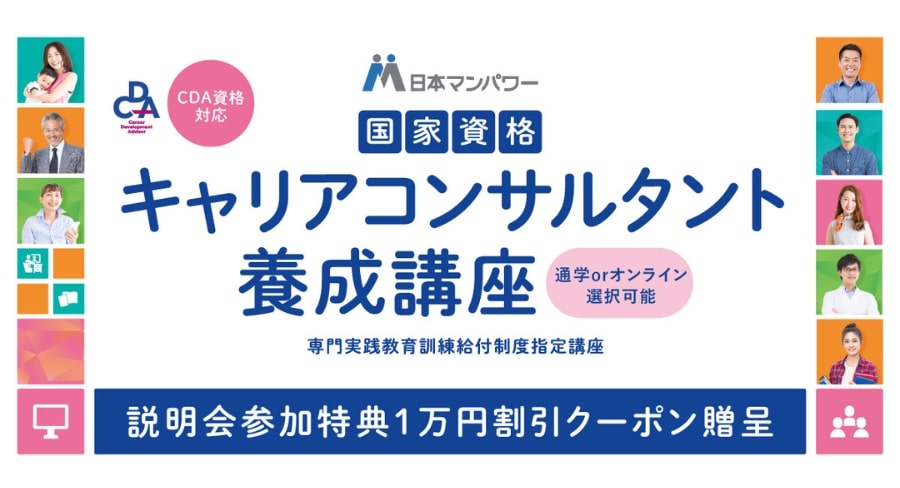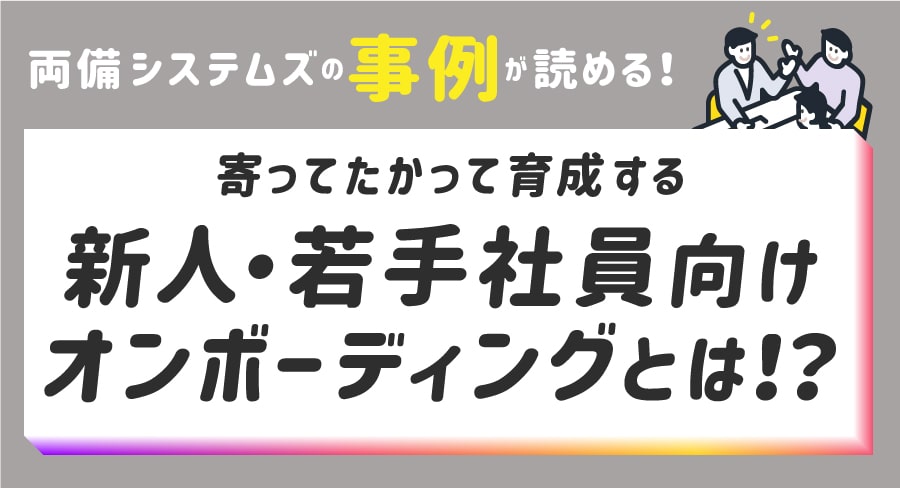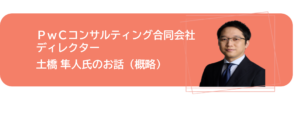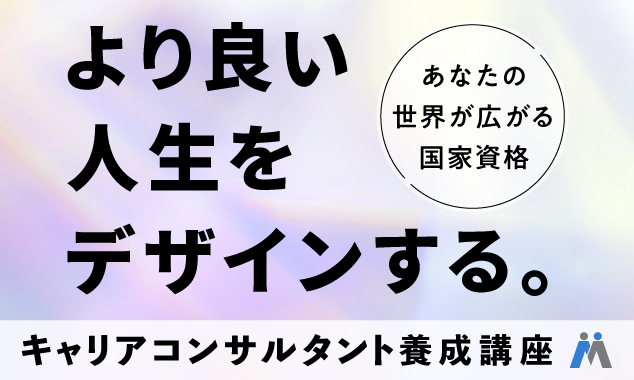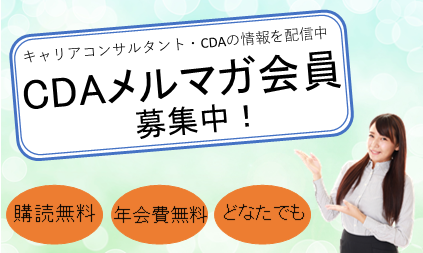「これからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~」の内容をご紹介するイベント 第4回目。今回のテーマは、9つのテーゼの中の『生産性と人間性を両立させよう』です。
ゲストはPwCコンサルティング合同会社ディレクター土橋隼人氏です。ご講演とパネルディスカッション、質疑応答を通して、このテーマについて深めました。ぜひご覧ください。
目次 ※クリックすると各章にジャンプします
1.主催者からの挨拶

キャリアのこれから研究所 所長 水野みち
「生産性と人間性」と聞いて、皆さんはどのようなイメージを持たれるでしょうか?
「人間性」とは、人間の本来の性質を意味し、「共感力」「承認欲求」など社会性を示す側面、「ユーモア」「好奇心」「想像する力」などのクリエイティビティに類するもの、または生き方の姿勢につながるような「意思を持つ」や「意味を考えようとする」などがあります。
ソクラテスも、ヴィクトール・フランクルも、人間が問い、意味を見つけることは人間が人間である上で欠かせないことだと重要視しました。
一方で、「生産性」とは、効率よく成果を生む力と言えます。生産性ばかりを追い求めても、味わいがなくなり、つまらなくなることがありますし、人間性ばかりを追い求めたことで時間がかかりすぎたといったジレンマは少なくありません。他にも、一律の全体対応と個別の丁寧な対応、納期重視と芸術性の追求などもジレンマの例です。
-水野さんからは、今回のテーマの入り口になる問いが語られました。
今回着目したかったのは、生産性と人間性をジレンマではなく、相乗効果として融合させていくことはできないかという問いを探求するためです。
この問いに答えることが、キャリア自律の実現につながると思っています。人間性を生かした生産性向上というのはどういう姿なのか。個々人の選択、裁量、個性の発揮、多様な価値観の尊重は、時間がかかるものです。しかし、上手に発揮されることで生産性が向上すると信じています。
キャリア自律が促進されることによって生まれる生産性とは、一体どのような姿なのか。そこにしっかりと目を向けていこうというのが今回のテーマになります。皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。ここからは、土橋隼人さんにご登場頂き、生産性と人間性というテーマでお話いただきます。
2.土橋氏登場

PwCコンサルティング合同会社
組織人事・チェンジマネジメント ディレクター
土橋 隼人氏(どばし はやと)氏
組織人事・チェンジマネジメント ディレクター
土橋 隼人氏(どばし はやと)氏
今日は、今私が気になっている2つのことについて、お話ししていきたいと思います。
1つ目はここ最近、人材マネジメントのフォーカスポイントが少し変化してきているということ。これは人間性と絡む話だとは思うのですが、今まで一律・一様でやっていたものを、個人の志向性や価値観の多様性を踏まえて、個別性の高いマネジメントをやっていきましょう、という風になっているというのが最近の特徴です。この話をしていきたいと思います。
2つ目は、人的資本経営と情報開示の必要性の高まりです。いわゆるビジネスに貢献するための人事をやり、その取り組みや効果を開示していきましょうという話です。これは昔から言われているけれどなかなかやれていないという問題があったのだとは思います。この領域のテーマについてもお伝えしますし、生産性の問題にも絡むと思っています。
人事の皆さんが、経営陣や投資家から「そもそも人事の取り組みは何のためにやっているのか?」「それはビジネスにどのようなインパクトがあるのか?」といった指摘を受けるようになったという話を私も最近よくお聞きします。そのあたりのお話ができればと思います。
3.土橋氏のお話 ~気になる2つのこと~
-土橋氏が最近気になっている2つの点について、本日の「生産性と人間性を両立させよう」というテーマとからめて、土橋氏の専門領域から問題提起をしていただきました。
(1)人材マネジメントの変化~個別性への着目~
人材マネジメントのフォーカスポイントが少し変化してきているとお話しましたが、大きくは次の3つの変化があります。
①全体性から、個別性の高いマネジメントへ
人材獲得競争の激化や価値観の多様化(への認識)によって、従来の全体の一律的な管理から、個々人の価値観や志向性を踏まえた個別性の高いマネジメントの必要性が叫ばれています。
人材獲得競争の激化や価値観の多様化(への認識)によって、従来の全体の一律的な管理から、個々人の価値観や志向性を踏まえた個別性の高いマネジメントの必要性が叫ばれています。
②対象・領域が曖昧に
ハイブリッドワークの拡大によって職場/家庭、仕事/私生活という時間的・空間的な境界は曖昧になり、人材マネジメントの対象も拡大しつつあります(ウェルビーイング、Work Tech 等)。
ハイブリッドワークの拡大によって職場/家庭、仕事/私生活という時間的・空間的な境界は曖昧になり、人材マネジメントの対象も拡大しつつあります(ウェルビーイング、Work Tech 等)。
③仕事の進め方が人間的に
HR/Work Techツールの普及によって仕事の進め方はより「人間的」になりつつあります(ボタンでの操作から、チャットボットとの会話を通じた操作等)。様々なツールも、機能的であることはもちろんですが、人間性へ配慮あるものに進化してきています。
HR/Work Techツールの普及によって仕事の進め方はより「人間的」になりつつあります(ボタンでの操作から、チャットボットとの会話を通じた操作等)。様々なツールも、機能的であることはもちろんですが、人間性へ配慮あるものに進化してきています。
(2)人的資本経営・情報開示におけるアウトカムへの注目
●人的資本経営・情報開示への注目度は高いのですが、多くの企業は施策の紹介にとどまっており、「人的資本経営のアウトカムは何か?」が問われているという、大企業に共通する課題があります。
●情報開示において、各社進めている取り組みが二極化している傾向が見られます。具体的には、つぎのような二極化です。
A.個人の志向性やニーズをあまり考慮しないものになっている(動機づけを欠いた自律的なキャリア開発 等)
B.個々人のみにフォーカスが当てられており、関係性(コラボレーション等)や組織文化などにあまり手が打たれていない
A.個人の志向性やニーズをあまり考慮しないものになっている(動機づけを欠いた自律的なキャリア開発 等)
B.個々人のみにフォーカスが当てられており、関係性(コラボレーション等)や組織文化などにあまり手が打たれていない
★土橋氏のお話をさらにご覧になりたい場合は、下のバナーをクリックしてください
4.パネルディスカッション
-ここからはパネルディスカッションです。モデレーターはキャリアのこれから研究所プロデューサーの酒井章氏です。
※下の写真は、左から酒井氏、ゲストの土橋隼人氏、水野
※下の写真は、左から酒井氏、ゲストの土橋隼人氏、水野

(1)EX(Employee Experience)という領域に関心を持ったきっかけは?
土橋さん(以下敬称略):私がEXの領域に取り組み始めたのは2016年、17年ぐらいです。当時の日本では「EX」についてはあまり知られていませんでした。なぜ私がEXに注目をしたかというと、私自身は30代で一般的な企業の中では若手と言われるタイミングで、多くの企業で実施されている人事施策に当事者として若干違和感がありました。個人の志向性や価値観はあまり考慮されず、働く人たちが均一的だという前提の下で一律・一様の施策が行われている中、自分たちの声はどこに伝わってるんだろう?と。ひとりの働く人間として違和感を覚えていたことがテーマになると思ったのが理由です。
酒井:土橋さんは、著書「EX従業員エクスペリエンス~会社への求心力を強くする人事戦略~」も2024年に出されましたね。元々はアメリカで発祥したEXが今、日本で注目されている理由は何だと思いますか?
土橋:2つありますが、一番は「人材不足」だと思っています。人材獲得も大変で、転職が当たり前になってきています。これまでは買い手市場だったのが、今では企業がいかに選ばれるかということが採用における重要テーマです。
2つ目は、やはり先ほどお話した通り、価値観の多様化に気がづいたということだと思っています。私自身は、価値観が多様化してきているとはあんまり思っていません。おそらく今までもいろんな志向性を持った方や働き方に制約を抱えていらっしゃる方はいて、価値観自体は多様であった。それにも関わらず一律的なもの(人事施策)をやっていたのではないでしょうか。それが最近、たとえ属性が同じであっても価値観は違うんだ、ということに気づいたということが大きい。以上2点だと考えています。
水野:EXは元々、CS(顧客満足度)やCX(カスタマーエクスペリエンス)という顧客の心理や行動を観察する方法から誕生したと聞いています。顧客の満足度向上を研究したら、次第に、従業員へのケアも大切だということに気がついたという、とても大切な視点からEXが生まれているんですね。
自分たち(従業員)が満たされていないと顧客にも良いサービスができないという、仕事はやりがいや生きがいを生むものというウェルビーイングの考えにもつながりますし、全体やつながりを俯瞰的に見るという持続可能性を大切にする考え方にも基づいています。
(2)EXにおけるテクノロジーの重要性
酒井:EXの中で、テクノロジーの重要性について教えてください。
土橋:従業員1人ひとりに合わせてコミュニケーションすることは非常に素晴らしいことではあるものの、従業員規模が例えば数千人になった瞬間に、それって可能なんですか?という疑問が人事の方からは出てくるのではないかと思うんです。
昔の人事の人たちは1人ひとりの家族構成まで理解していたと言われますが、人事部門の仕事も増えていますし現代だとなかなか難しい。そのような中で、そこ(一人ひとりに合わせたコミュニケーション)を可能にするのはテクノロジーの力なのかもしれないと思っています。
酒井:土橋さんは先日、ラスベガスで開催された「HRテック・カンファレンス」に参加されたと伺いました。そこで感じた、最先端のHRテックをご紹介いただけますか?
(3)HRテックのトレンド
土橋:HRテックでも今年はやはりEXがキーワードになっていました。従業員の成長や成功をサポートすることが強化されていました。これについても、生産性と人間性の二つの局面からご紹介します。
「生産性」の話でいうと、それを高めていくツールは非常に多くなっていると感じました。無駄な手続きを無くし、一つにまとめていくことで利便性を高める話は非常に重要なテーマでした。
「人間性」の点では、冒頭にお伝えした働き方が人間的になっているという話に加えて、企業側が従業員のエモーショナル(感情的)なところやプライベートなところまでケアをするようなツールが増えてきていると感じました。
例えば、従業員が抱えている日々の支払いをわかりやすく表示し、知らせて、ケアしてあげるといったものもありましたし、余裕を持たせるような仕組みやサービスもありました。これも、単にお知らせするだけではなく、かなりエモーショナルなところや人間性に配慮した通知が工夫されていましたし、内容も私生活までをケアをしているなという感想を持ちました。
(4)折り紙の箱で包まれたマカロン
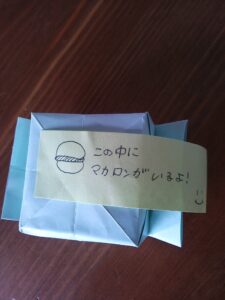
水野:ヒューマンタッチはすごくいいですね。昔、すごく忙しくて心が荒みそうな時、私のデスクに折り紙の箱がおいてあったんです。中にマカロンが入っていました。同僚が「差し入れでもらったマカロン、水野さんが不在の間に乾燥しちゃいけないから、箱に入れておきました」と言ってくれて。
私は、それだけで1ヶ月くらい元気をもらった感じがしました。こういうヒューマンタッチはすごくパワフルです。人が頑張れるとか、仲間のために無理ができるとか、笑顔が生まれるというのは、こういう優しさや思いやりによるものも大きいですよね。それを逆にAIから思い出させてもらうというのも、微妙な話ですが…もっと意識したいと、土橋さんの話を聞いて考えさせられました。
(5)人的資本経営について
酒井:今、人材育成がうまくいっていないということですが、これは、なぜだと思われますか。
土橋:一つは個人への動機付けをあまり意識していないのではないかとは思っています。「人材開発やキャリア自律を重視して取り組んでいきます」と経営者や人事の方はおっしゃいますが、ではそれをやったところで、個人にとってどんなハッピーなことがあるのかというようなところはあまり語られていないようです。自律的に学ぶことによって自分の将来のキャリアが開けるのか?理想のキャリアに近づくための機会にチャレンジできるようになるのか?といった方面の仕組みの整備はあまりされていないと感じています。
一方で、そもそもそうしたケアが全員に必要なのかという議論もあります。組織側がちゃんと支援をしないといけない、責任を負わなければいけないと言いながら、若干個人に責任を押し付けているのではないかな、とも思えます。動機づけの話と、個々人に責任を押し付けているのではないか。その2点が、いまひとつ、うまくいってない要因だと思っています。
酒井:会社側にしてみれば「いろんな学びのツールを用意しているから自主的にやって欲しい」といことですね。でも社員がなぜか使ってくれない、という話を私もよく人事の方からお聞きします。私が感じているのは、その育成というのはやはりDXやリスキリングに代表されるように、ハードスキルに寄っているところがあるんじゃないかと思います。ソフトスキルの部分というのが追いついていなくて、まさにそこが人間性に関わってくると思います。
土橋:おっしゃる通りですね。どうしてもスキルというとテクノロジー関係に注目が集まりがちだと思っています。全体的にソフトスキルには注目が集まっていないですし、議論も十分にされていないと思っています。
DXを例にとった場合、デジタルツールを使えるようになることがゴールなのかというと、多分そうではなくて。それを活用して仕事をするためには、新しいものに対するマインドセットを持ったり、試すようなことがあったりといったフットワークの軽さみたいなものも必要ですよね。いろんな概念があるにもかかわらず、若干ハードスキルに寄ってしまっていることは私も感じていることです。
酒井:このポイントはまさに人材育成に携わられている水野さんからご覧になっていかがでしょうか。
水野:そうですね。先ほど土橋さんのお話の中で、従業員の声を聞こうというものがアメリカで注目を集めてるという話を聞いて、これも人的資本経営の流れの中でかなり重要なポイントになってくるのではないかと思ってます。
キャリア自律しなさい、リスキリングしなさいと言われても、自分たちの選択肢は少ないし声も聞いてもらえない、裁量もあまりない、失敗は足をすくわれる、という経験が長らく積み重なってきた側からすると、急に能動的にとはいきません。「またやることが増えるのか…勘弁してほしい」というのが率直なところではないでしょうか。
そこを、人事側が消極的だと判断せずに社員に対して成長を促していく姿勢を持ち、制度、仕組み側も変わる姿勢や余地を示しながら、従業員の声を辛抱強く聞いていくという姿勢や仕組みが大切だと思います。労使の信頼関係を取り戻す上で、実はこういうところでもキャリアコンサルタントの能力は役立つのではないかと思っています。
(6)組織文化について
土橋:組織のパフォーマンスを考えた際に、「個々人の能力が上がるだけでは組織全体の力は上がらない」というのは大事なポイントだと思います。ですから、組織文化は大事です。とはいえ、社内でボールを持つ組織がはっきりしないことで「それって人事がやる仕事ですか?」「誰がやる仕事ですか?」と、議論がストップしてしまうようなことがあるのかなと思っています。
酒井:この組織文化、水野さんが仕事を通じて感じられていることはありますか?
水野:担う組織がないという問題はその通りですね。私も長年企業内のビジョン浸透やカルチャー改革、組織開発に携わってきましたが、組織の文化を変えるには最低でも3年、長くて5年とか10年たってやっと組織文化が変わってくるものだと感じることが多いです。
マインドなどの内側からと、仕組みなどの外側からの変化を生む工夫が必要です。トップのコミットによるプロジェクトが立ち上がることも多いのですが、推進者が腹落ちし、人の心が動く、共感できる、想いが乗っている、みんなのために、といった熱意と信頼関係が必要だと思います。ここにも生産性と人間性の視点が当てはまりそうですね。
酒井:この組織文化について私が感じているのは、日本の企業は創業者の理念を大切にする部分があると思うのですが、逆にそこに引きずられてきたような側面があるということです。ですので、やはり守っていくべきものと、変えるべきものをきちんと仕分けする必要があるのではないかと思います。
(7)生産性と人間性の両立を実践している企業とは?
土橋:例えばうまくいってない組織を見て、働く人に対するケアにのみフォーカスして取り組んでいる会社が多いように感じています。人事の人たちはどうしてもケア寄りになりがち、というところがあるのかもしれません。ケアをすることと厳格なパフォーマンスマネジメントは両輪であることを認識しないといけないのではないでしょうか。
もう一つは、今日出て来たようなEXや学びのテーマに通底する考え方として人と組織の関係が対等になっているかということが結構大事なポイントなのかもしれません。お互いが対等に要求し合ったりわかり合ったり、説得し合うみたいなところがないといけない、と思います。
酒井:人と組織の関係は対等になっているか、これについては、水野さん、いかがでしょうか?
水野:じつは先週、スウェーデンのストックホルムで、サステナブルな活動の国際会議に参加してきました(IDGサミット)。そこでは、組織の運営や進め方が日本と全く違っていると実感しました。オープンで、フェアで、フラットで、民主的に物事を進めていく。その分、時間はかかりますが、個々人が安心してコミットすることができます。
先ほど土橋さんが「対等」とおっしゃいました。その対等であるという体験を日本で働く私達はあまり経験したことがないのではないかと思うのです。対等どころか、上下関係のお作法から学ぶことがほとんどではないでしょうか。そのため、対等のイメージがわかない。北欧では、民主的な対話の方法や対立の仕方を小学校から学ぶそうです。
それがないために、みんなの意見を聞いたら混乱してしまう、反対意見が出てきたら面倒だ、と思ってしまう。そういったメンタルモデルを持つ人が日本の組織には多いとしたら、そこからではないでしょうか。
対等に物事を議論して決めていくんだという体験を蓄積していくことで、先ほどの組織文化づくりに繋がっていくのではないかと思います。社会実験みたいなものをもっと組織の中でやっていく必要があるんじゃないかなと感じました。
酒井:私も付け加えるとすれば、個人と組織の関係性の面ですごく重要なのが入口だと感じています。「心理的契約」という言葉がありますが、採用の時点で入ってくる人たちにきちんと人として向き合えているかが、その後の関係性を決定づけると思います。
では改めて、これからの生産性と人間性の両立について、どのようなことが必要になってくるのでしょうか。土橋さん、いかがでしょうか。
土橋:非常に本質的で難しいご質問ばかりで、なかなか悩ましいのですが、生産性と人間性は両輪だと思っています。個人的に気になっているのは、人間性と生産性は、特に人事や経営の場面では、ポジションや立場によってどちらを取るかが分かれやすいということです。
人材開発系のお仕事をしている人は比較的人間性ベースで動いている一方、労務や企画系の方は生産性ベースで動いていたりするようです。これは、あまり健全ではないなと私は思っているんです。ポジションとスタンスによって視点が変わるというよりは、全ての人がこの両輪を考えていくという前提に立つ必要があるのではないかと思っています。
5.ブレークアウトセッションとクロージング
酒井:ここからはご参加の皆さん同士の対話の時間に入っていきたいと思います。
(1)ブレークアウトセッション・全体シェア
-今回のイベントでも、参加者同士でグループに分かれ、感想を共有する時間を設けました。グループで挙がった感想で、特に印象深かったコメントを1つご紹介します。
「生産性との両立人間性との両立ということだったんですが、この2つは、対立するもので考えるのではなく、渋沢栄一さんがおっしゃったそうなんですが、道徳と経済は同一という、元々それは突き詰めれば同一のものではないかというお話が出ました。」
(2)水野からクロージングの言葉
水野:土橋様、ありがとうございました。生産性と人間性というテーマから、自分や組織の在り方について問われるような深い考察ができたと感じています。次回のテーゼのイベントは、「多様性と複雑性」です。本物のMBTIを日本で広げてきた第一人者の園田由紀先生にお越し頂きます。本日はご参加を誠にありがとうございました。
◆お知らせ◆
●企業内キャリアコンサルタントの寺子屋(通称キャリテラ)について
「これからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~」のイベントは、キャリテラの会員登録(無料)をするとご参加いただけます。
ぜひ、こちらからご登録ください!
「これからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~」のイベントは、キャリテラの会員登録(無料)をするとご参加いただけます。
ぜひ、こちらからご登録ください!
●パフォーマンスマネジメントについて
マネジャーの皆さんは、ケアだけでなく、パフォーマンスをマネジメントできていますか?成果を上げるための1on1は出来ていますか?課題を感じている方はこちらのサービスもご覧ください。マネジャーのPM力を向上させるeラーニング
マネジャーの皆さんは、ケアだけでなく、パフォーマンスをマネジメントできていますか?成果を上げるための1on1は出来ていますか?課題を感じている方はこちらのサービスもご覧ください。マネジャーのPM力を向上させるeラーニング
●日本マンパワー キャリアコンサルタント養成講座 紹介割引制度のご紹介
日本マンパワーのキャリアコンサルタント養成講座は、質と満足度の高いプログラムとして口コミによるお申込みが多いのが特長です。そのため、ご紹介者への感謝の気持ちを込めて、紹介割引制度を設けました。キャリアコンサルタント有資格者からの紹介で、キャリアコンサルタント養成講座にお申込みいただいた方に、受講料割引などの特典をご用意しております。
お知り合いで、受講検討中の方がいらっしゃいましたら、こちらの「紹介割引制度」をぜひご活用ください!
日本マンパワーのキャリアコンサルタント養成講座は、質と満足度の高いプログラムとして口コミによるお申込みが多いのが特長です。そのため、ご紹介者への感謝の気持ちを込めて、紹介割引制度を設けました。キャリアコンサルタント有資格者からの紹介で、キャリアコンサルタント養成講座にお申込みいただいた方に、受講料割引などの特典をご用意しております。
お知り合いで、受講検討中の方がいらっしゃいましたら、こちらの「紹介割引制度」をぜひご活用ください!
キャリアカウンセラー&社労士。趣味は映画・ドラマ鑑賞、ヨガ。ヨガの得意技は頭のてっぺんで立つポーズ。
この記事はいかがでしたか?
ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!
シェアはこちら
RECOMMENDED関連おすすめ記事
人気記事
-
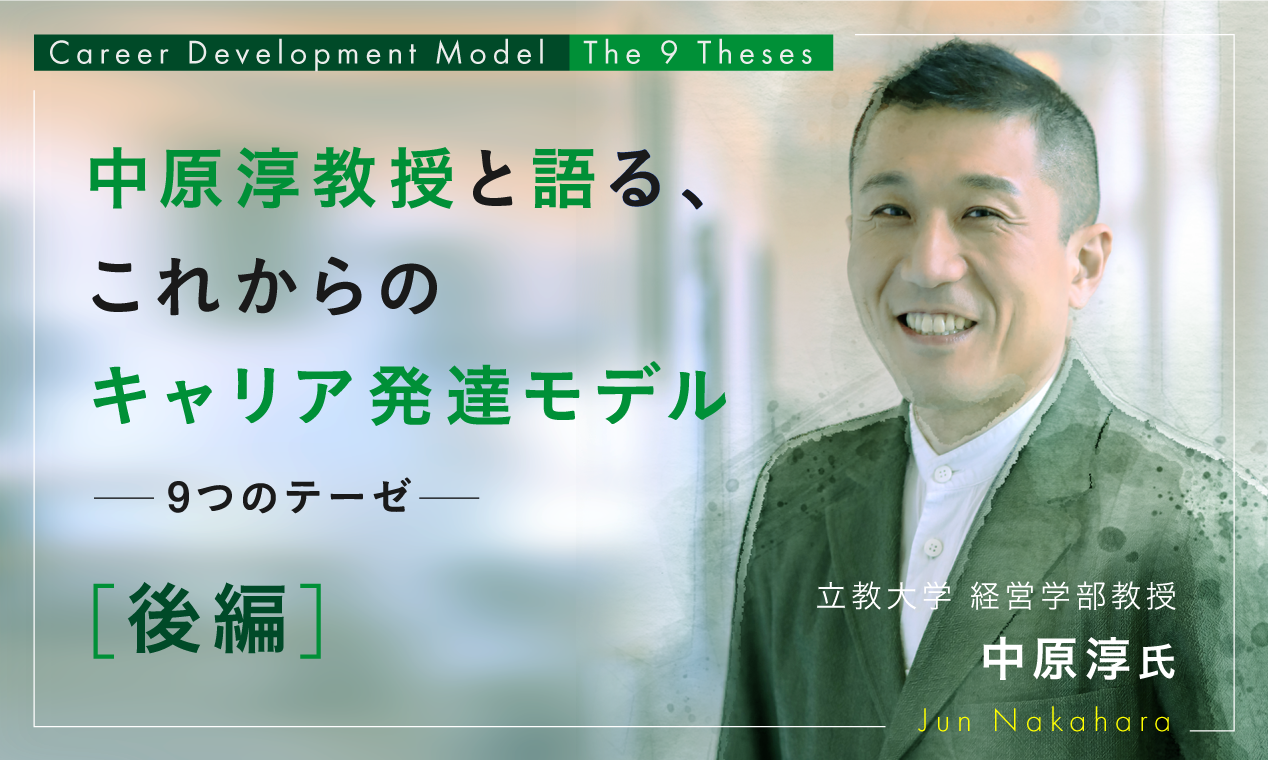
PICK UP
イベント
【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~
2022.8.29
-

PICK UP
イベント
【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~
2022.4.22
-
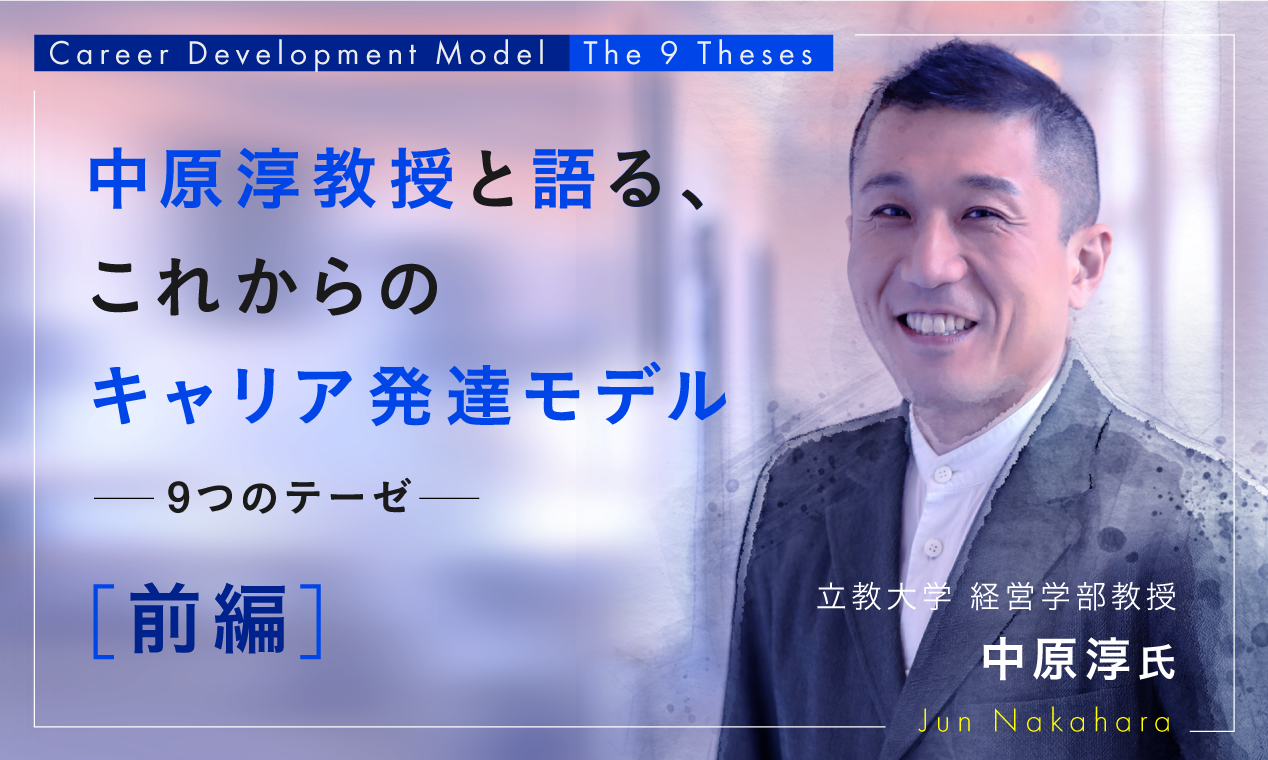
PICK UP
イベント
【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~
2022.4.19
-
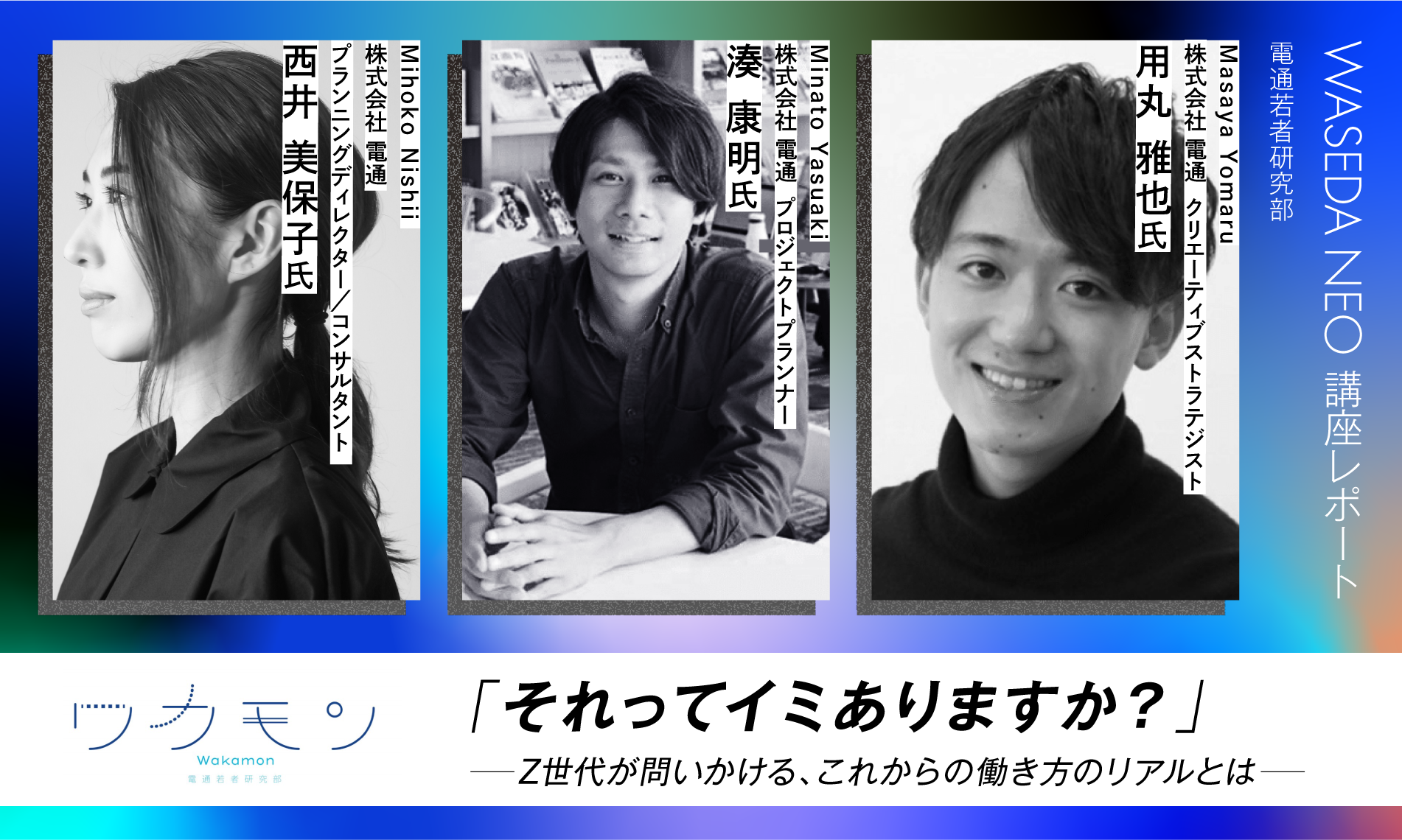
イベント
「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-
2022.2.8
-

PICK UP
特集記事
ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり
2020.12.28
-

インタビュー
個人
マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)
2020.12.4
-

インタビュー
個人
マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)
2020.10.30