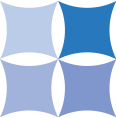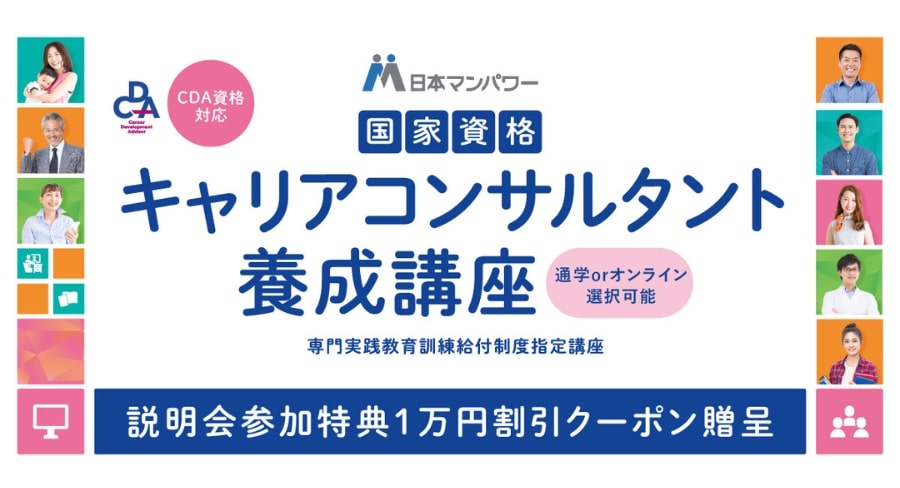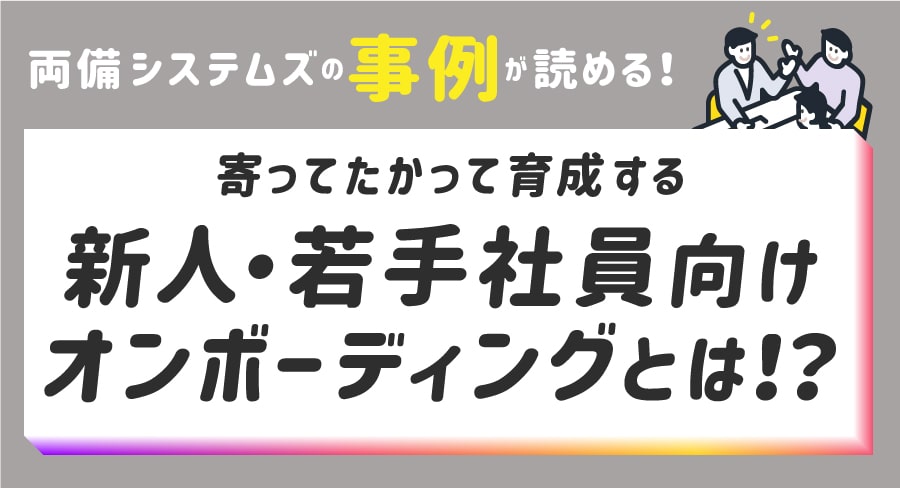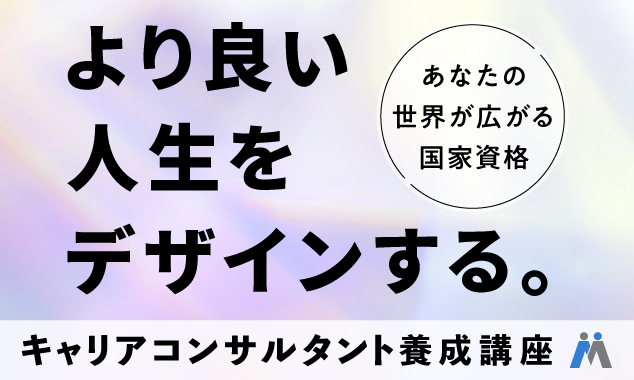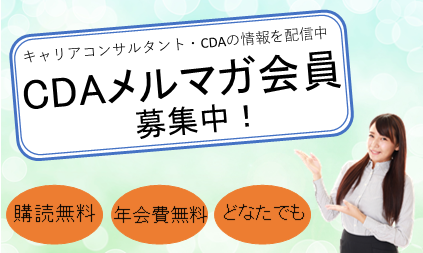「これからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~」の内容をご紹介するイベント。第9回目(最終回)は「つながりを感じよう」をテーマに開催。
冒頭、キャリアのこれから研究所所長の水野みちが講演を行いました。続いて、キャリアのこれから研究所のプロデューサーである酒井章氏進行のもと、水野も交えてパネルディスカッションを実施。その後参加者の皆さまと共にこのテーマについての豊かな対話の時間へとつながっていきました。
●イベント実施日 2025年3月24日
●「これからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~」詳細ページは、こちら
●執筆:原博子 キャリアカウンセラー
1主催者挨拶
つながりを感じよう 自分や他者とのつながり
~みんながいるから自分がある~
私たちは誰もがつながりの中にいます。つながりを感じられると、人は居場所を持つ感覚が芽生え、自分が自分であって良いと感じ貢献意欲が育まれます。しかしつながりが感じられないとき、自分のことでさえ他人ごとにしてしまうことがあります。つながりとは何か?つながりを感じる上で何が大切なのか、一緒に考えていきたいと思います。

キャリアのこれから研究所
所長 水野みち
水野:今日のテーマは「つながり」。いよいよ3月末という節目の時期です。4月から新たな環境に身を置くという方もいるそんな時期だからこそ、「つながり」というテーマで皆さんとお話しをするのを楽しみにしています。
自分と他者とのつながり。みんながいるから自分がある。私たちは誰もが、つながりの中で生きています。
この世に生まれるということは、既につながりの中にいるということです。どこかから生まれ、誰かの支えがあって生を受けている。つまり、生まれたその瞬間から、私たちはつながりの中で生きているのです。そして、誰かの世話なしに生きている人はいません。自分が気づいている以上に、多くの人の支えや助けを受けながら、私たちは命をつなぎ、今日まで生きてきました。そして、私たち一人ひとりも誰かの「つながり」を支えています。
ただ、この「つながり」は、いつも実感できるものではないかもしれません。つながりを強く感じるときもあれば、全く感じられないときもあります。いかがでしょうか?
つながりを感じることができると、人は「ここが自分の居場所だ」と思えるようになり、自分が自分であってもいいんだ、と肯定感を持つことができます。そして、誰かの役に立ちたい、貢献したいという意欲も自然と育まれます。
一方で、つながりを感じられないとき、人は「自分のこと」でさえ「他人事」のように思ってしまうことがあります。例えば、自分が選んだことなのに、「なんとなく自分で選んだ感じがしない」と感じることはありませんか?
「あれは仕方なく選んだんだ」とか、「あのとき、誰々のせいでこうなったけど、自分には責任がない」というように、どこかで他人のせいにしたくなることがあるかもしれません。仕事でも、似たようなことが起こることがありますよね。
「あの出来事は自分のことにしたくない」「他人事にしておきたい」――そう思うこと、ありませんか?
水野:これは、一体何がそうさせているのでしょうか?
皆さんは、自分や他者とつながりを感じられていますか?
これは、私たちのホームページにも掲載している「9つのテーゼ」の一文に通じる問いです。
●「これからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~」詳細ページは、こちらです。こちら
みなさんにとって「つながり」のイメージはどのようなものですか?
(この問いに対して、チャットに皆さんが続々と書いてくださいました)
「安心感」、「居場所」、「温かさ」、「感謝」、「分かり合える関係」、「信頼感」
みなさん、書き込みをありがとうございました!
2水野の話
(1) つながりの効果 ~サーベイ結果から~
水野:ここで、私どもの実施しているキャリア自律サーベイの結果をご紹介したいと思います。
サーベイで取得した数千人の結果によると、「つながり」は、「組織コミットメント」・「ワークエンゲージメント」・「キャリア満足度」にも強く影響を及ぼしていることが分かっています。この「つながり」は、キャリア自律を伸ばしていくときに重要だということが分かります。日本は他国よりもエンゲージメントが低いというデータもありますが、「つながり」について考えてみると共に、何が今の組織に必要なのかを見つめ直してみるのも一つかもしれません。
(2) Belongingは、安心できる場、心理的な所属感、一体感
水野:そしてもう一つ、最近では「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)」に「BA」という言葉を加えた「DEIBA」という新しい概念が登場しています。「A」はアクセシビリティ、つまり障壁を減らそうという動きです。
ここで私が注目したいのが、「B」の「Belonging(心理的な所属感)」という言葉が含まれている点です。この「Belonging」は、安心できる居場所や心理的な所属感を意味します。
これまでのダイバーシティ推進の取り組みは、例えば「女性活躍推進の数値目標を増やす」といった数字に焦点が当てられがちでした。しかし最近では、こうした心理的な状態にも注目しようという動きが生まれています。つまり、ただメンバーとして名前があるだけではなく、その人が「安心できる居場所」を感じられるか、所属感を持てるかという視点が重視されるようになってきているのです。
この話に関連する切り口として、「静かなる退職」という現象があります。この言葉は、職場には在籍しているものの、心の中では既に会社から離れてしまっている状態を指します。立場や役職、メンバーとしての名前は登録されているものの、自分がその場で安心できる居場所を感じられず、心理的な所属感を持てていない状態です。このような状況では、たとえ「ダイバーシティを推進しています」と掲げていても、実際にはその人の気持ちはその場にいない、ということが起こり得るのです。
DEIBA=Diversity,Equity,Inclusion,Belonging、Accessibility
ここでのBelongingは、安心できる場、心理的な所属感という意味を持ちます
(3) 何がつながりを感じられる要因になるのか
水野:次に皆さんと考えたいのは、「何がつながりを感じられる要因になるのか」ということです。
私たちは、これまでさまざまなつながりに関する調査や研究に目を向けてきました。その中で、やはり一番しっくりくる答えが、心理学者アルフレッド・アドラーが提唱した「共同体感覚」でした。
では、何があれば共同体感覚が生まれるのでしょうか?
アドラーが挙げた要素として、以下の三つが重要だとされています。
1. 所属感・信頼感
2. 自己受容
3. 貢献感
この中でも特に「貢献感」というのは見落としがちかもしれません。小さなことでも、「ありがとう」という言葉の持つ意味を実感します。
(4) 「貢献」と「自己受容」
水野:まずは「貢献感」について、アメリカの学校に転校したばかりの自分の中学時代のことをお話ししたいと思います。
授業の後、理科のクラスの先生にこんな風に言われました。
「ミチ、どうして手を挙げてこのクラスで発言しないんだ?それじゃぁ、貢献にならないよ」と。
クラスでは静かに座っていることが正しい事と教えられていた私は、先生のその言葉に驚いてしまいました。
しかし、そうかそうかと、次の授業までに教科書を読み込み、頑張って手を挙げて発言するようにしました。
すると今度は、こんなことを言われました。
「ミチ、それは教科書に書いてあることだろう?教科書に書いてあることをただみんなの前で発言するだけでは、クラスへの貢献にはならないよ、あなたがどう思っているか、何を感じたかを話してくれることが貢献になるんだよ」と。
この経験は、当時の私にとっては驚きの連続で、少し厳しいものでしたが、今振り返るととても貴重な学びでした。「貢献する」ということは、自分の考えを共有し、その場に自分を投入することが大切なのだと教えてくれたのです。「あなたが貢献できるのはあなたが何を感じ、何を見て、このとき何を思ったかを発言してくれることだよ」 と。この先生の言葉によって、自分の中には嬉しい感覚が沸き起こりました。正解とか、正しさからみんなの役に立つことではなく自分が自分であることがこのクラスへの貢献になるんだと先生に言われた感じがしたからです。
皆さんの組織の中では、どうでしょうか。その場への貢献感が感じられているでしょうか。
次に注目したいのが「自己受容」です。 自分自身を受け入れられていないと、人を遠ざけたくなることがあります。また、冒頭にも触れましたが、受け容れられていない自分の特性を、他者に投影してしまうことがあります。
以前、園田由紀先生に「多様性」をテーマにご登壇頂いた際にも、似た内容が語られていました。自分を受け入れられないとき、自分の中の「好きではない部分」や「隠したい部分」を、外側の世界に投影してしまうことがあります。つまり、自分の中の「悪魔」を他者や環境に見つけ出そうとしてしまうのです。その結果、自分のことなのに「他人事」のように感じてしまうこともあります。
だからこそ、つながりを感じるためには、「自己受容」が大切だと言われています。
(5) つながりの落とし穴 ~境界線の大切さ~
水野:そして、もう一つお伝えしたいのは、つながりの負の側面です。
「つながり」の話をすると、時に「つながりが煩わしい」とか「つながりと言われると、協調性を強要される印象があるから苦手」とか「集団圧力を感じる」という声も聞きます。
そうなんです。心地の良いつながりではなく、居心地の悪いつながりもあるのです。この際に大切なのは、適切な「境界線 Boundary」を引けるかどうかだと思っています。
これは家族療法の世界で学ぶ内容なのですが、健康的な関係には、適切な境界線があると言われています。境界線というのは、心理的な距離です。人と人との間に、自分が居心地のいい心理的距離を線引き出来ているかどうかです。この線の場所は、その日の自分の心境や成長によって変わってきます。
これが「ぐちゃっ」としてしまっている状態を「Enmesh(纏綿状態)」と呼びます。例えば、隣の人のイライラなのに、あたかも自分がイライラしているように錯覚してしまうことがあれば、それは纏綿状態かもしれません。言い換えれば、境界線がうまく引けていない状態です。
誰かの課題もそうです。となりの人の課題なのに、あたかも自分の課題のように背負い込んでしまう。頼まれごとも、本当は嫌なのに断れない、いつも誰かの機嫌を気にしている、など。これも、纏綿状態かもしれません。この境界線が上手く引けずに苦しくなると、人は「ぶちっ」と関係を切り離してしまうことがあります。
逃避の状態でいなくなるか、極端に無関心の状態になるという状態が生まれます。 職場でも、そういう人はいるかもしれません。境界線を上手く引けず、辞めてしまうなど、そのつながりを断ち切るしか、対処方法が見つからないという状態です。あまりにも集団の意識が強く、コミットメントやエンゲージメントを高めようと、つながりを強要しすぎてしまう組織においては、注意が必要かもしれません。
特に私達は、教育現場で境界線のことを教えられることはほとんどありません。アメリカが全部良いと言っているわけではありませんが、アメリカでは「自分の境界線を引く」ということを教育の中でも教えられたりします。自分を大切に出来ているだろうか?とセルフチェックすること、断る勇気を持つこと、相手を失望させることに罪悪感を抱きすぎないこと、など。
ドラマを見ていると、「私には人間関係の境界線の引き方に課題がある(I have boundary issues)」というセリフが時々出てきます。それくらい割と一般的な話となっています。これ以上は踏み込ませないっていう境界線を引くということで、仲が悪くなるということではなく、仲を良くするためにちゃんと境界線を引くということが大切なんですね。 そのためにも、人や組織に対して支配的になりすぎず、柔軟に、近づいたり少し離れたりといった関係の変化も大切だと言えます。
3パネルディスカッション~参加された皆さまを交えての対話~
~キャリアのこれから研究所プロデューサーの酒井氏の進行のもと、水野を交えてのパネルディスカッションになり参加された皆さんを交えての豊かな対話の時間になりました。~

酒井です。よろしくお願いいたします。キャリアこれから研究所の設立に関わり、現在プロデューサーという形で関わらせていただいています。
改めて、水野さんにとって「つながり」とはどんなイメージですか?

「時と空間を共にする」というイメージです。
■参加者の皆さまを交えての対話の時間
~参加者の皆さんの中で、数名の方が、カメラオンにしてコメントをくださいましたので紹介します~
参加者Uさん
私の子どもは、新型コロナウイルスの感染拡大が続いていた時期に高校へ入学しました。そのため、入学式は通常より遅れて6月に行われました。さらに、給食の時間も会話をせず、自分の席で黙々と食事をするよう求められたり、互いに距離を取ることが徹底されたりと、非常に制限の多い環境でした。その結果、先生によると、コミュニケーションがうまく取れない子が増えているとのことでした。
人生で最も多感な時期に、他人との距離を取らざるを得ない状況に置かれた子どもたちの中には、身体的な感覚やコミュニケーション能力が十分に育まれなかった子もいるのではないか、と私は感じていました。
そんな状況の中で私が考えたのは、「リアルでコミュニケーションを取れないとは一体どういうことなのか」ということでした。彼らは他人との人間的な距離感を保つのが難しい一方で、SNSやデジタルツールに関しては、生まれながらに慣れ親しんだ「デジタルネイティブ世代」として非常に器用に使いこなしています。しかし、どこか「距離感がバグっている」とでも言うべき状態があるように感じました。
また、私たち大人が「Z世代」と名前を付けて、彼らを一括りにしてしまっていることが、世代間のギャップを生んでいる部分もあるのかもしれません。こうしたリアルとデジタルの間にあるギャップについて、改めて考えさせられました。

「リアルなコミュニケーションとは何か?」という深い問いとともに、学校での子どもたちの様子や世代間のギャップについてのお話をありがとうございました。お話を聞いて思い出したのが、令和5年における不登校の増加に関するニュースです。不登校の子どもの数は前年比で約4万人増加し、過去最多となったとのことでした。その理由も、いじめなどの問題ではなく、「なんとなく行きたくない」「学校に意味を感じられない」といった声が多いと報じられています。
こうした現状を見ると、おっしゃる通り、コミュニケーションの前提そのものが問われる時代に入ってきているように感じます。個人的にはそれを悲観的に捉えるばかりではなく、強制されるコミュニケーションが減り、自分の意思でコミュニケーションのあり方を選べるようになってきた面もあるのではないかと思います。それは、これからの時代における新しい「つながり方」の可能性を示しているのかもしれませんね。
49つのテーゼのサイト紹介~今までの振り返り~
水野:最後に、これからのキャリア発達モデルのサイト(こちら)をご紹介します。ぜひリンクは自由に紹介いただいて結構ですのでこの考え方そのものもぜひ、従業員の皆さんの対話にお役立ていただけると嬉しいなと思っています。
また、今までのイベントレポートのリンクもご紹介させていただきます。
第1回 複線と伏線 こちら
第2回 年齢を超えよう こちら
第3回 葛藤と向き合う力 こちら
第4回 生産性と人間性を両立させよう こちら
第5回 ビジョンとリアリティの両感覚を磨こう こちら
第6回 計画しつつもアジャイルな行動を取ろう こちら
第7回 あるべき自分とありたい自分の両方を意識しよう こちら
第8回 多様性と複雑性を大切にしよう こちら
皆さんにとっては、どのテーゼが一番自分にとって印象的でしたか?
よかったらチャットに記入をしていただければと思います。
(1) 参加者との対話
Tさんからのコメント テーゼ『計画しつつもアジャイルな行動を取ろう』について
私が就職した頃は、会社の研修で「PDCAサイクルをきっちり守ること」が徹底的に教え込まれていた印象があります。しかし、最近では、社会が目まぐるしく変化する中で、じっくりとプランを立てている時間がない、という現実に直面しているのだと感じます。
私自身、研究開発の分野に長く携わってきた経験があるのですが、その中で研究を進める過程でテーマが変わったり、状況に応じて柔軟に対応する必要があったことを何度も経験しました。そうした背景から、状況に応じて素早く対応しながら進めていく「アジャイル」という考え方にとても興味を持つようになりました。これからの社会では、こうした柔軟性がますます重要になっていくのではないかと感じています。

山崎さんの「大きな妄想、小さな実験」という言葉は、ご自身の開発経験から生まれたものです。その意味で、Tさんが経験されたこととすごく共通すると思いましたし、キャリア全般にも通じる普遍性を持った言葉なんだ、と改めて確認できて嬉しかったです。
Kさんからのコメント テーゼ『自分の中の多様性』に関しての体験談
私は、沖縄県宮古島という人口55,000人ぐらいの島で生まれ育ちました。その後アメリカに留学して勉強した後、日本に戻ってきて、現在は外資系企業で働いています。ですので、自分の中の多様性を含めて、いろいろな組織や人々の価値観に触れながらそれを楽しんでいる環境にいます。その意味で、「自分の中の多様性」というテーゼには腹落ちしましたし、モチベーションも高まって、感謝を申し上げたいです。

ありがとうございます。 みなさんの感想から、こちらが素敵なプレゼントをいただいた気持ちになっています。Kさんの腹落ちやモチベーションの高まりについてもう少し教えて下さい。
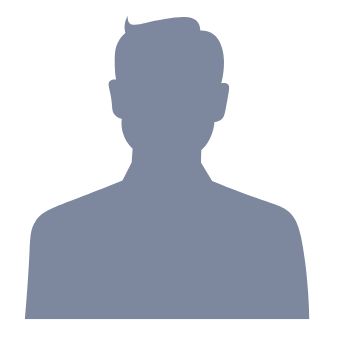
自分が今生きていることや、家族のありがたさや、娘が生まれてきたことや、妻と出会ったことや、「すごくシンプルな当たり前のことに気づく」ことも人間にとって大事で、そのありがたさを知る上で「本音の繋がり」が私にとって理想です。

まさにつながりが生まれる幸福、つながりから生まれる幸福って感じがしますね。 ありがとうございました。
(2) 9つのテーゼに込める願い

9つのテーゼを開発したメンバー間では、皆さんが、キャリアを考えることをもっと楽しいと思ってもらえたらという願いを共有していました。
最近、「キャリアハラスメント」という言葉があると聞きます。「将来どうなりたいの?」とか「キャリアプランは?」と聞かれるのが嫌だという社員も増えているそうです。キャリアを考えることが苦痛だという言葉を聞くたびに、「キャリアを考えることで、もっとみんなが楽になって自分のことを好きになる、そんな社会になるといいな」と思っています。 それがひいては、つながりをもっと感じられるし、いろんな多様性も許容していくような社会になるのではないかと思います。
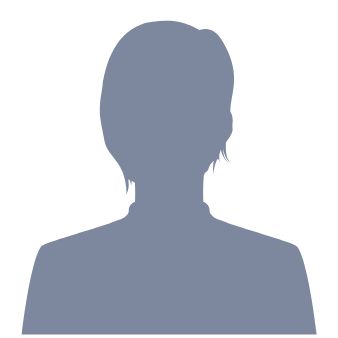
「今のキャリアを考えることが楽しい」と思えるようになるには、1人ひとりがどのようなマインドセットや意識を持つべきでしょうか?
仕事によっては、毎日が同じ作業の繰り返しであったり、製造ラインの中で同じ仕事を続けるような環境もありますよね。そうした中で、「つながり」や「やりがい」「喜び」を感じることは、言葉で言うほど簡単ではないのではないかと思います。
水野さんがおっしゃった「キャリアを考えることを楽しむ」という考え方は、とても重要だと感じています。ただ、それを実際に多くの人に感じてもらうには、どのようなアプローチや働きかけが必要なのでしょうか?日々の単調な業務の中でも、その人なりの「意味」や「価値」を見つけられるようなサポートや工夫が必要なのかもしれませんね。ぜひ、その具体的な方法についても教えていただけると嬉しいです。

これはあくまで私のやり方なんですが、日常を過ごす中で「物事を細かく見る」という意識がとても大切だと思っています。例えば、駅まで歩いている道すがら、「今日はこんな鳥を見かけたな」とか、「あのランドセルを背負った子供たちの後ろ姿、もうすぐ1年生から2年生になるのかな」と感じること。あるいは、「職場であの人、あの話をしている時に嬉しそうだったな」と気づくことでも構いません。日々の何気ない景色を、もっと丁寧に、細かく見ていくのです。
そうすると、普段は見過ごしてしまうような1日の中にも、実はとても豊かなものがたくさん詰まっていることに気づきます。そして、私たちの心は、そういった小さな出来事に対して実は頻繁に動いているんですよね。例えば、美しい景色を見て「綺麗だな」と感じたり、どんよりした天気に「あれ、夕焼けの色が違うな」と思ったり、満員電車で「この人、すごい圧があるな」と感じたり——これらもすべて心が動いている瞬間です。その「心の動き」にもっと意識を向けて、細かく感じ取ることで、自分の中にどれほど多くの豊かな感覚が詰まっているかに気づくことができるのです。

これが、私がキャリアコンサルタントという活動を好きな理由でもあります。
他者という存在が、私たちの「網の目」をきめ細かくしてくれることで、人は自分の体験やその日1日に起こった出来事を丁寧に振り返り、味わい直すことができるんです。評価・判断せずに、聴いてくれる人がいるということ。そして、その出来事の奥にある「自分の願い」や「本当に求めているもの」、さらには「どんな価値観が潜んでいたのか」ということを発見できるようになります。
そういったプロセスを通じて、その人自身の「美しさ」(真善美の「美」)が浮かび上がってくるんですよね。誰もがそのような美しさを持っています。

ですが、私たちは日々の忙しさに追われて、つい「やるべきことをこなすだけ」になったり、「正しく効率的に動き回る」という状態になりがちです。私自身もそうした日々を過ごしてしまうことが多いです。でも、ふとした夜に立ち止まって振り返ると、意外な発見があったり、いろいろなことを思い出せたりします。
そのきっかけは、たとえば「9つのテーゼ」でもいいですし、誰かの言葉でもいいと思います。それをきっかけに振り返ってみると、「キャリアを考えることって面白いな」「自分の感覚や経験が、実は自分に多くのことを教えてくれていたんだな」と実感できるはずです。そして、自分がしてきた選択にはちゃんと意味があったんだ、と気づけるのではないでしょうか。

今の水野さんのお話に関連して、Nさんのお役に立つかもしれないと思い、少し補足させていただきます。
水野さんが仰っていた中で、私が特に大切だと感じたのは、「日常の中に潜むものを細かく見ましょう」というメッセージです。これはつまり、「観察する」ということですよね。
私自身、製造や研究開発といった部署に長く携わってきましたので、ルーチンワークのように見える仕事を経験してきました。ただ、それでも全く同じことの繰り返しというわけではないんです。製造プロセスでも、日々少しずつ何かが変化しています。でも、そうした変化を「ざっくり捉える」だけだと、何も気づけないまま過ぎてしまいます。
逆に、その小さな変化を観察し、気づきを得ることで、自分の成長や喜びにつながるものを発見することができます。こうした観察や気づきを積み重ねていくうちに、日々の仕事や取り組みに対して「意味」や「価値」を感じられるようになってくるんですよね。これは、日常をより豊かにしてくれる視点だと思います。
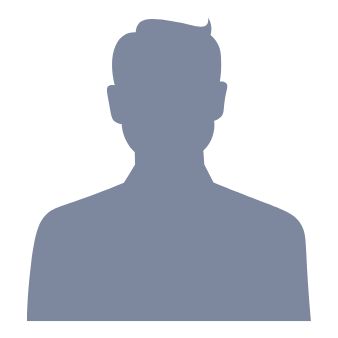
ありがとうございます。皆さんのお話がとても参考になりました。今日参加して良かったですし、また、思い切って質問して良かったです。ありがとうございました。

こちらもありがとうございます。 ご質問いただいたことでNさんとのつながりを感じられましたし、またTさんもこうやって登場していただいてつながりを感じられる瞬間でした。本当にありがとうございます。
~ある方の発言からインスピレーションを得て、また新たな方が言葉を発していく、まさに「つながり」をこの場で見たような瞬間でした。~
5クロージングの言葉

酒井さん、最後にこの9回通して酒井さん自身、どんなことをやられましたでしょうか?

本当にこのテーゼのイベントのプロセスそのものがアジャイルそのものでした(笑)。 もう来月どうしようと。どんなゲストの方をお呼びしようかみたいな話は本当にアジャイルしながらやって来ましたが、結果的に本当に多方面の専門家の方々のご意見をいただくことで、我々テーゼの開発者側が一番学ばせていただいた時間だったのではないかと思っています。

酒井さんのおかげでこの9回開催することができたなというふうに思っておりますありがとうございました。改めて、テーゼを一緒に創り上げてきた、高橋浩さん、伊達洋駆さん、日本マンパワーの和泉と嶋も、いずれもこの企画に携わって一緒にですね、展開してくれたものを、本当に感謝してます。この9つのテーゼは哲学だと酒井さんはおっしゃってくださったんですが、まさに哲学でもあり、また皆さんの中で自由に進化をさせて、役立てていただけるといいなと思います。
キャリアをもっと楽しく、面白くしていってください。この変化の激しい時代にこそ、皆さんが、ほっと安心できる時間を作れることを心から願っております。 本当にありがとうございました。
管理者です
この記事はいかがでしたか?
ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!
RECOMMENDED関連おすすめ記事
人気記事
-
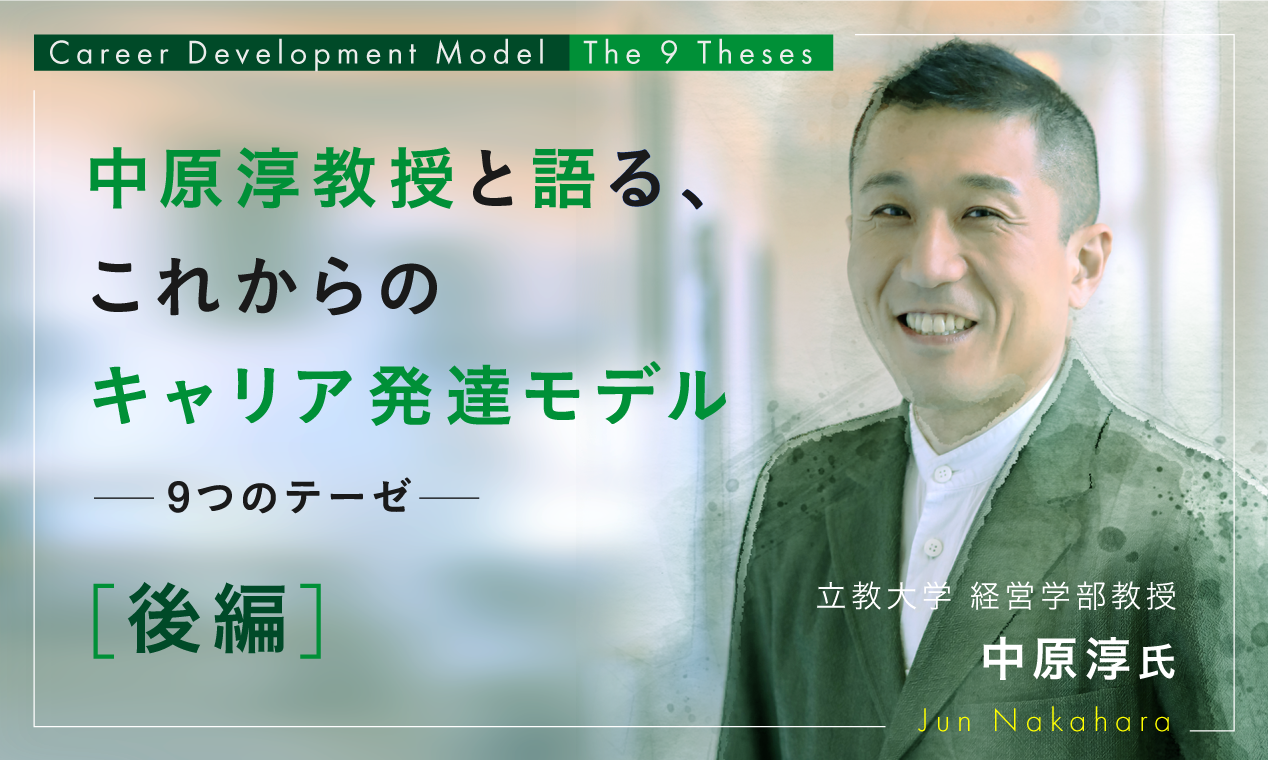
PICK UP
イベント
【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~
2022.8.29
-

PICK UP
イベント
【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~
2022.4.22
-
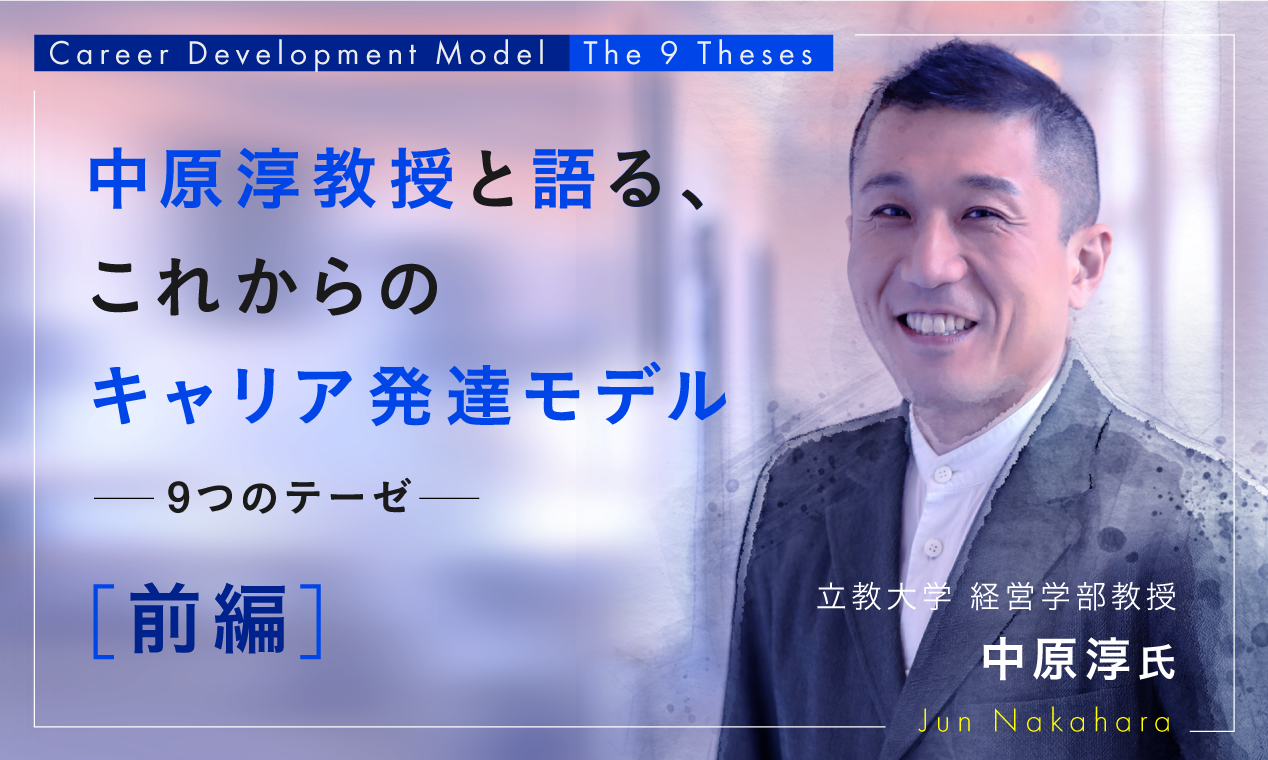
PICK UP
イベント
【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~
2022.4.19
-
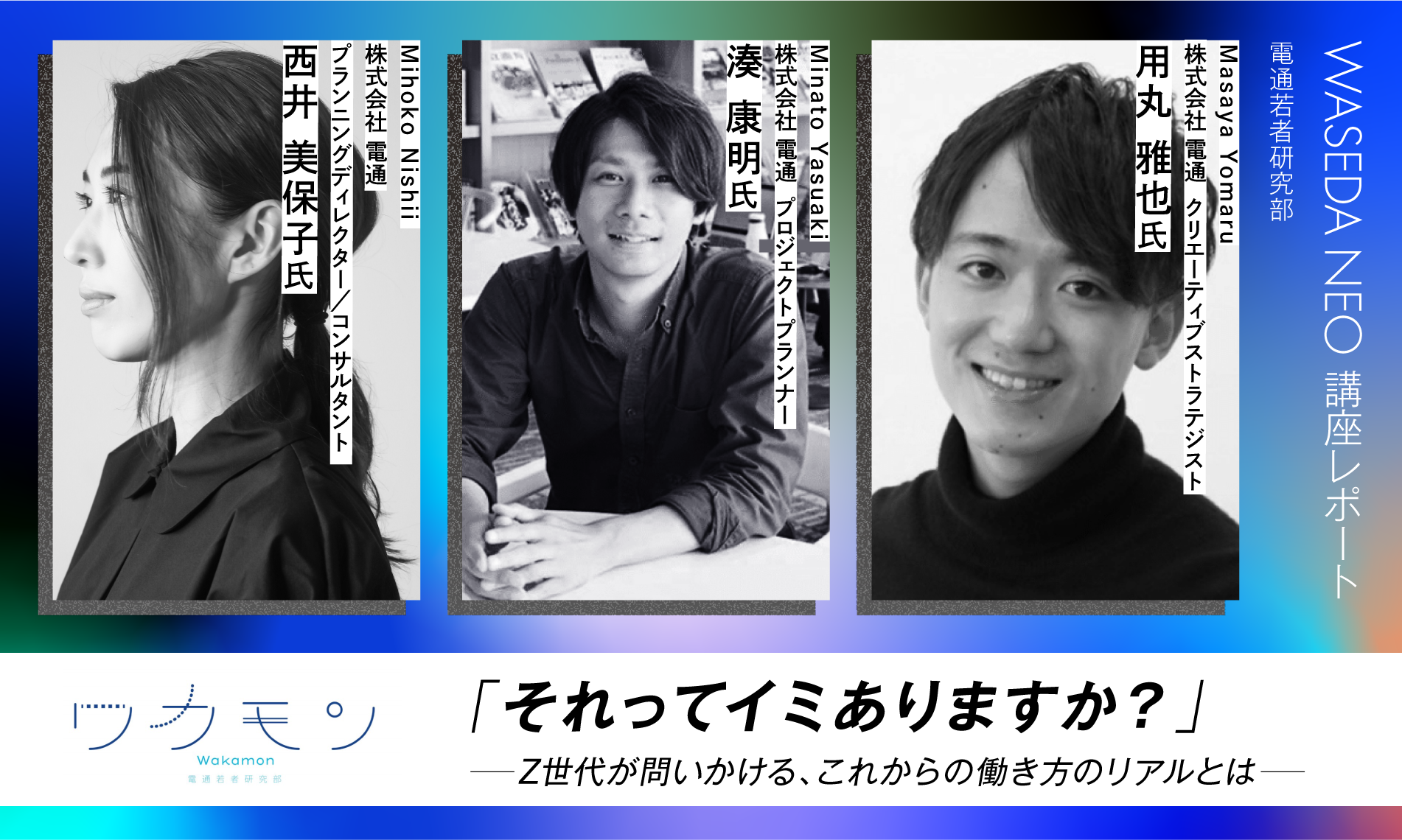
イベント
「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-
2022.2.8
-

PICK UP
特集記事
ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり
2020.12.28
-

インタビュー
個人
マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)
2020.12.4
-

インタビュー
個人
マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)
2020.10.30